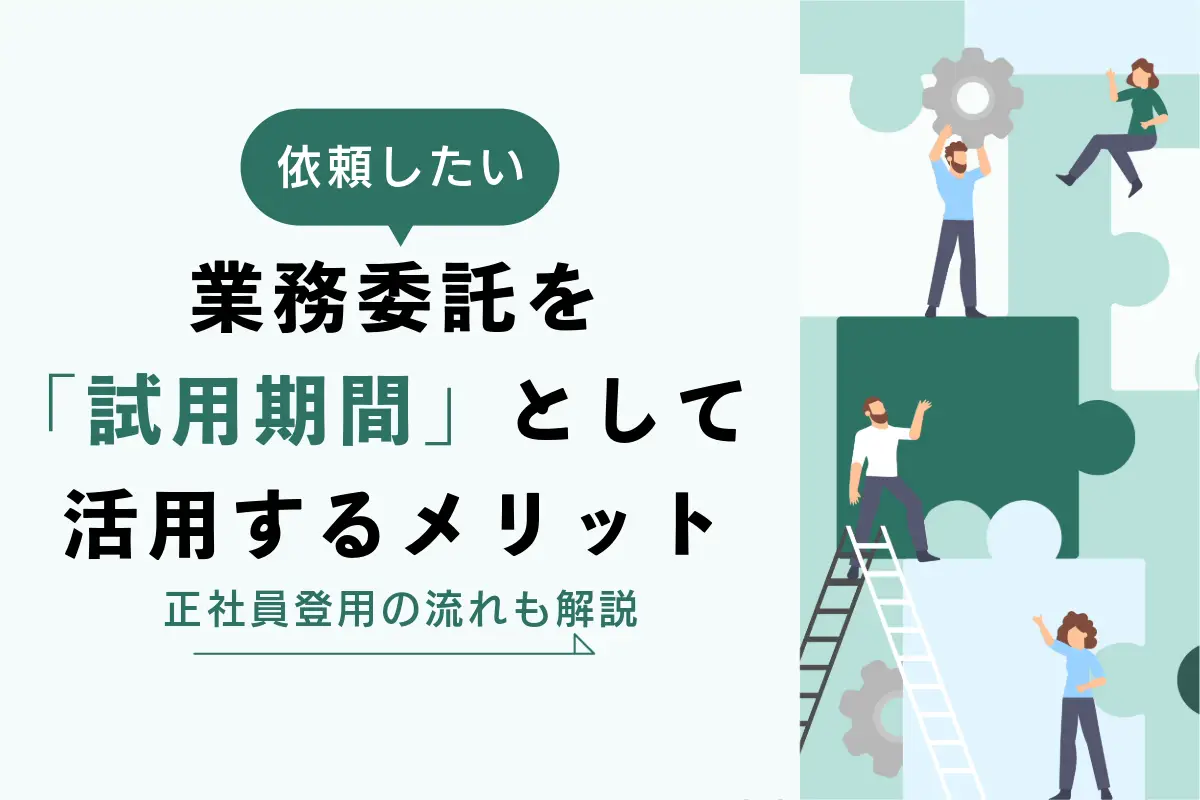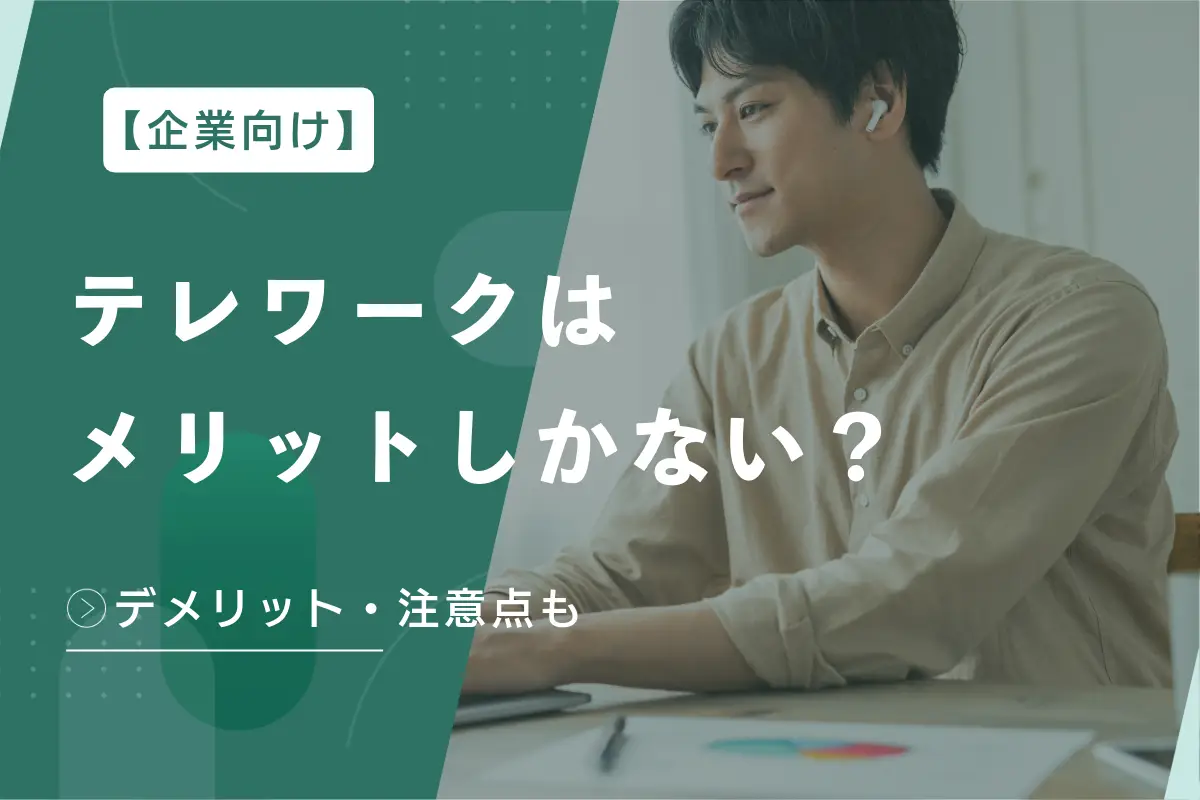「正社員採用する前に、まずは業務委託で様子を見たい」そんなニーズを持つ企業が、近年増えています。業務委託を「試用期間」のように活用することで、コストを調整しながら採用のミスマッチを防止できます。しかし業務委託期間中、指揮命令の出し方によっては、「偽装請負」とみなされる恐れもあるため慎重な対応が必要です。
この記事では、業務委託を試用期間として活用するメリットや注意点など、解説していきます。また、優秀な外部人材を正社員登用する際の流れについても紹介。「正社員採用で試用期間を設けるべきか悩んでいる」「業務委託が気になっている」といった企業は、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも試用期間とは?
試用期間とは、企業が人材の適性や能力を見極める際に設ける期間のことです。試用期間中、企業は人材の勤務態度やスキル、適応力を確認できます。正社員採用の場合、一般的に「1〜6か月程度の試用期間」とするケースが多いです。なお、試用期間を設定する際は、「求人票に試用期間を明示すること」が職業安定法で定められています。
また社会保険は、法律上の雇用契約や本人の同意に関係なく、加入要件を満たす場合は試用期間の当初から社会保険の被保険者に該当されます。試用期間中に解雇したい場合は、合理的な理由が必要です。安易な打ち切りはトラブルの元となるため、誠実に対応していきましょう。
参考:e-Gov 法令検索-職業安定法施行規則四条 / 日本年金機構-適用事業所と被保険者 / 厚生労働省(確かめよう労働条件)-試用期間
雇用契約と業務委託契約の違い
「試用期間」という名称に法律的な定義はなく、雇用契約・業務委託契約のどちらでも使用されることがあります。一般的に正社員の本採用前の数ヶ月間を「試用期間」とするケースが多いですが、業務委託契約でも「試用期間」という言葉が使われることがあります。
たとえば、業務委託で仕事を依頼していた外部人材を、正社員登用する場合です。業務委託の期間中は、外部人材のスキルをチェックする「試用期間」となり、正社員登用の可否を判断できます。
業務委託契約は、そもそも雇用契約とは異なる契約形態です。以下では、雇用契約と業務委託契約の違いをまとめました。
項目 | 雇用契約 | 業務委託契約 |
指揮命令関係・労働時間の拘束 | あり | なし |
勤務地の指定 | あり | 原則なし |
報酬の支払い | 月給や時給など | 成果ベース、業務完了ごと |
社会保険の適用 | あり | なし(原則、個人が国民保険に加入) |
解雇や契約解除の制限 | 解雇には合理的理由が必要 | 比較的自由に契約終了が可能 |
上記のように、両者には明確な違いがあります。業務委託契約を「試用期間」とする場合、実態が雇用契約とならないよう、注意しましょう。
▼関連記事:業務委託と正社員、どっちがいい?両者のメリットや正社員登用のステップまで解説
▼関連記事:【企業向け】正社員と契約社員の違いとは?両者のメリット・デメリットを解説
正社員採用前に業務委託を「試用期間」とする3つのメリット
ここでは、正社員採用前に業務委託を「試用期間」とするメリットについて解説します。
1.採用のミスマッチを防止できる
通常の正社員採用では、一度雇うと簡単に契約を解消できません。採用後にスキルや価値観の不一致が発覚して早期離職すると、育成や採用にかかった時間やコストが無駄になります。
そこでおすすめなのが、まず業務委託で一定期間プロジェクトに参加した後に、正社員採用を打診する方法です。業務委託を「試用期間」とすることで、実際の業務からスキルや相性を見極められます。
また、業務委託期間中に、候補者側も社風や業務内容を体験できるため、入社後のギャップによるミスマッチを防ぎやすくなります。お互いの納得感を高めたうえで雇用契約に移行できる点は大きなメリットです。採用の精度を高めたい企業は導入を検討してみましょう。
2.スポット登用で外注費の調整がしやすい
いきなり正社員として雇用すると、月給や賞与、社会保険料などの固定費が即座に発生します。仮に採用後にミスマッチが起きれば、再採用や早期退職にかかるコスト・手間も重くのしかかります。
その点、「業務委託から正社員登用」という採用なら、最初は業務委託として外部人材にスポット的に業務を依頼できるため、リスクを最小限に抑えられます。業務量や事業フェーズに合わせて、稼働時間や業務範囲を柔軟に調整できるため、「まずは月○時間だけ」「繁忙期だけ依頼する」といった段階的な関わり方も可能です。事前に委託料を設定すれば、予算管理もしやすいでしょう。
3.企業と求職者、双方が気軽に仕事を始められる
雇用契約の締結や社会保険の加入など、正社員採用では試用期間の時点でやるべきことが多いです。早期離職が起きると、時間的・金銭的な損失も避けられません。
その点、業務委託契約であれば、よりカジュアルに仕事を始められます。契約手続きが比較的シンプルで、業務内容や稼働条件も柔軟に設定できるため、スタート時のハードルが低いです。企業と求職者、双方が以下のようなメリットを実感できるでしょう。
- 【企業側】即戦力人材をすぐに現場にアサインできる
- 【求職者側】雇用に縛られず、自分に合った働き方を試せる
- 【共通】「まずは一緒に働いてみる」という選択が可能
また、転職市場にはいない層との出会いも期待できます。「まずは副業として関わりたい」「自分のスキルを業務で試したい」といった層とも接点が生まれる点は、業務委託契約ならではのメリット。柔軟な関係性から始められるため、お互いの理解が深まったうえでの正社員採用となり、人材の定着も期待できます。
業務委託を「試用期間」とする際の注意点
ここでは、業務委託を「試用期間」とする際の注意点について解説します。
偽装請負に気をつける
業務委託契約を「試用期間」として活用する際には「偽装請負」に気をつける必要があります。形式上は業務委託契約でも、実態が雇用契約とみなされる場合、法的な問題が発生します。
偽装請負とは、本来は指揮命令関係がないはずの業務委託契約において、企業が業務の進め方や勤務時間などを細かく指示し、実質的に従業員のように扱っている状態を指します。以下のような業務の進め方となっている場合、偽装請負と判断されやすいので注意しましょう。
- 勤務時間や出社日を企業が指定している
- 担当業務の進め方を細かく指示している
- 自社の社員と同じ場所・チームで常時働かせている
- 「平日9〜18時は必ずオンラインで待機してください」と指示している
偽装請負に該当すると、労働基準監督署からの勧告や、法的トラブルへの発展といった事態になりかねません。雇用契約と業務委託契約の違いを区別しておきましょう。
報酬の支払い方法や期日を明確にする
業務委託契約では、報酬の支払いが「給与」ではなく「業務に対する対価」として扱われます。そのため、支払い方法や期日があいまいだと、トラブルに発展するリスクが高まります。たとえば次のような点は、契約前に必ず合意し、書面に残しておきましょう。
項目 | 概要 |
報酬額 | 成果物1件ごと、または月額など、報酬の算出方法を明記 |
支払い方法 | 銀行振込・PayPalなど支払い手段の確認 |
支払い期日 | 納品日から何日以内に支払うか(例:翌月末払い) |
成果物の定義 | 納品の範囲や基準をあらかじめ共有する |
「毎月末締め・翌月25日払い」「業務完了後7日以内に指定口座へ振込」など、具体的な条件を契約書や合意書に記載しておきましょう。また支払いの遅延が続くと、信頼関係にも悪影響です。その後の正社員登用をスムーズにするためにも、適切な報酬設定で支払いが遅延しないようにしましょう。実務面でも、経理や契約管理のフローを整えておくと、継続的な連携がしやすくなります。
契約終了時の取り決めを明確にしておく
「業務委託から正社員登用」の場合、スキルや相性の不一致で、「正社員登用は打診せずこのまま契約を終了させたい」ということもあるでしょう。その時の取り決めが不十分だと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。試用的な位置づけで業務委託を活用する場合、契約前に以下のようなポイントを明確にしておきましょう。
- 契約終了のタイミング
- 更新や延長の有無・条件
- 成果物や納品データの取り扱い
- 正社員登用の判断基準
たとえば、「3か月の契約満了後に正社員登用を打診する可能性がある」「正社員登用を希望する場合は最終月に面談を実施する」など、あらかじめルールを定めておくと契約終了時の混乱を防げます。
また、契約終了後に「納品物の扱い方」がわかるよう、成果物の使用範囲や著作権の帰属についても、契約書に明記しておきます。良好な関係を維持するためにも、あいまいな点を残さず、合意形成をしっかり行いましょう。
業務委託(試用期間)から正社員登用する際の流れ
以下では、業務委託(試用期間)から正社員登用する際の流れを解説します。
1.業務委託契約と秘密保持契約(NDA)を締結する
まずは、企業と外部人材の間で業務委託契約書と秘密保持契約(NDA)を交わしましょう。それぞれ、以下の点に気をつけます。
契約書 | 内容のポイント |
業務委託契約 | 契約期間、業務内容、報酬、成果物などを具体的に記載する |
秘密保持契約(NDA) |
|
業務委託契約(フリーランスに委託する際)は、書面または電磁的方法で取引条件を明示することが法律で義務化されています。また、買いたたきや成果物の受け取り拒否なども禁止です。「試用期間」と言っても、業務委託契約を締結している間はフリーランス新法といった法律を遵守しましょう。
参考:フリーランス新法
2.仕事を依頼する
業務委託契約を締結したら、実際に業務の依頼を始めましょう。まずは以下の内容を明確に伝えることが重要です。
- 業務内容と納品物の定義
- 納期やスケジュールの目安
- 報告・連絡の頻度と手段
- 連携メンバーや使用ツールの案内
また、採用を前提とした試用的な位置づけである場合でも、フィードバックやすり合わせは実施します。業務を通じて相手の仕事の進め方やスタンスを確認しつつ、少しずつ信頼関係を築いていきましょう。
3.相性やスキルを確認した後、正社員化を打診する
一定期間の業務委託を通して、定着の可能性が見込めたら、正社員登用を打診します。以下のような観点で総合的に評価しましょう。
評価ポイント | チェック内容の例 |
スキル・経験 | 期待通りの成果物を納品しているか?/自走して課題を解決できるか? |
コミュニケーション力 | チーム内で円滑に連携が取れているか?/報連相が的確か? |
自社理解 | 企業理念やカルチャーに共感しているか?/自社の業務プロセスを理解・尊重しているか? |
このとき、「副業として続けたい」「フリーランスの働き方を維持したい」など、本人のキャリア志向も確認します。仮に正社員化を断られたとしても、業務委託契約で引き続き仕事を依頼することも可能です。いずれにしても、候補者との信頼関係を維持しておきましょう。
4.同意のもと、雇用契約を締結する
登用が了承されれば、雇用契約を締結します。雇用契約では、以下のような項目を明確に取り決めておくことが重要です。
- 雇用形態
- 給与・賞与・昇給制度
- 勤務地・勤務時間・残業の有無
- 福利厚生・社会保険
- 業務内容・所属部署・役職
- 試用期間の有無と条件
- 就業規則・服務規律の適用範囲
書面または電子契約で締結し、契約内容を確認・同意するプロセスを踏みます。業務委託のときと比べて、報酬体系や働き方が変わることも多いため、齟齬が生まれないように説明をしましょう。
また、雇用契約に切り替える前に、忘れずに既存の業務委託契約を正式に終了させます。登用時には、労働条件通知書の交付や、社会保険の加入手続きも迅速に対応しましょう。
▼関連記事:【企業向け】業務委託と正社員をどう切り替える?メリットや手続きの流れなど徹底解説
業務委託(試用期間)から正社員登用に関する、よくある質問
ここでは、業務委託(試用期間)から正社員登用に関する、よくある質問をまとめました。
Q1.業務委託経由で採用した人材が辞める際の対応を知りたいです。
業務委託契約において、人材が契約期間中または満了時に辞める(契約を終了する)場合は、事前の取り決めと適切な手続きが重要です。以下のポイントを押さえておくと安心です。
- 契約書で「契約終了」の条件を明文化しておく
- コミュニケーションを密に取り、突然の離脱を防ぐ
- 業務の棚卸・マニュアル化を並行して進める
業務委託契約では、正社員のような「退職」という概念はありません。代わりに、「契約終了」として扱います。以下の内容を契約書に明記しておくことで、トラブルを防止できます。
項目 | 内容例 |
契約期間 | 〇年〇月〇日〜〇年〇月〇日(更新の有無も記載) |
中途解約条項 | 双方の合意または〇日前の書面通知により解除可能 |
業務引き継ぎの義務 | 契約終了時には業務マニュアルの提出などを求める |
フリーランスや副業人材は複数の案件を抱えている場合も多く、意思決定のスピードが速い傾向にあります。こまめなコミュニケーションとフィードバックを通じて、関係性を良好に保つことで、突然の辞退や離脱リスクを下げられます。
また、いざ契約終了となった際に業務が属人化していると、後任への引き継ぎに負担がかかります。そのため業務内容のドキュメント化や権限管理の明確化など、日頃から業務委託契約の進め方やルールを整備しておきましょう。
Q2.業務委託で優秀な人材と出会うにはどうすべきですか?
業務委託だからといって、採用基準を下げる必要はありません。正社員採用と同等、またはそれ以上の目線で選考を進めましょう。以下は、優秀な人材と出会う秘訣をまとめました。
- スキル・実績重視で募集要項を設計する
- 業務内容に直結するスキルを求人票に明記する
- コミュニケーション力や主体性をチェックする
- 面談では、報連相の意識やチームとの相性も確認する
- 相場を踏まえた金額を提示する
- Workshipなど、実績ある業務委託人材が多く集まるサービスを利用する
効率よく外部人材と出会いたい場合は、フリーランス専門のプラットフォーム・人材紹介エージェントの活用をおすすめします。これらを活用すると、自社の業務内容や条件に合った人材をすぐに紹介してもらえます。
たとえば約5万人以上の外部人材が登録している『Workship 』では、求人作成や候補者の提案など、さまざまなサポートを受けられます。業務委託が初めての企業での使いやすいため、導入を検討してみましょう。
▼Workship:サービス資料のダウンロードはこちらから(無料)

Q3.スタートアップ企業が業務委託(試用期間)を活用する際の注意点を教えてください。
スタートアップにとって、業務委託はスピーディーかつ柔軟に必要な人材を確保できる手段として活用できます。ただし、運用を誤ると法的リスクやトラブルにつながるため、以下のポイントに注意しましょう。
- 業務開始前にカルチャーや価値観を共有する
- あらかじめ「正社員登用の可能性あり」と明記し、合意を取る
- 解約条件や引き継ぎ内容を契約書に定めておく
- 評価制度とフィードバックの設計をしておく
上記のように進めると、信頼関係を維持したまま正社員登用できます。契約内容や運用方法に不安があれば、社労士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
業務委託から正社員登用したい場合は、『Workship CAREER』におまかせ!
本記事では、業務委託を「試用期間」として活用し、正社員登用につなげるポイントを解説しました。「業務委託から正社員登用」の採用手法では、優秀な人材が離れないよう業務内容や評価基準などを伝え、安心して働ける環境を維持しておきましょう。
とはいえ、「自社にマッチする人材の見極め」や「定着率の向上」は簡単ではありません。そんなときは、『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』にご相談ください。
- トランジション採用の導入:業務委託契約からスタートし、その後正社員登用への切り替えを支援いたします。
- 豊富な人材データベース:エンジニア、デザイナー、PMなど、約5万人以上のフリーランスネットワークから、企業のニーズに合った候補者をご紹介いたします。
- 人事のプロが採用から育成まで一貫して伴走:人材育成の制度設計や労務管理など、貴社の人事課題をトータルに解決いたします。
Workship CAREERでは、豊富な人材プールとサポート体制のもと、企業様が安心して採用活動を進められるよう伴走して支援いたします。無料相談も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
▼Workship CAREER:サービス資料のダウンロードはこちらから(無料)

- Workship CAREERのサービス内容
- ご契約の流れ
- 取引実績
- 関連サービス

リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェント「Workship CAREER」の編集部です。採用に役立つ情報を発信していきます。