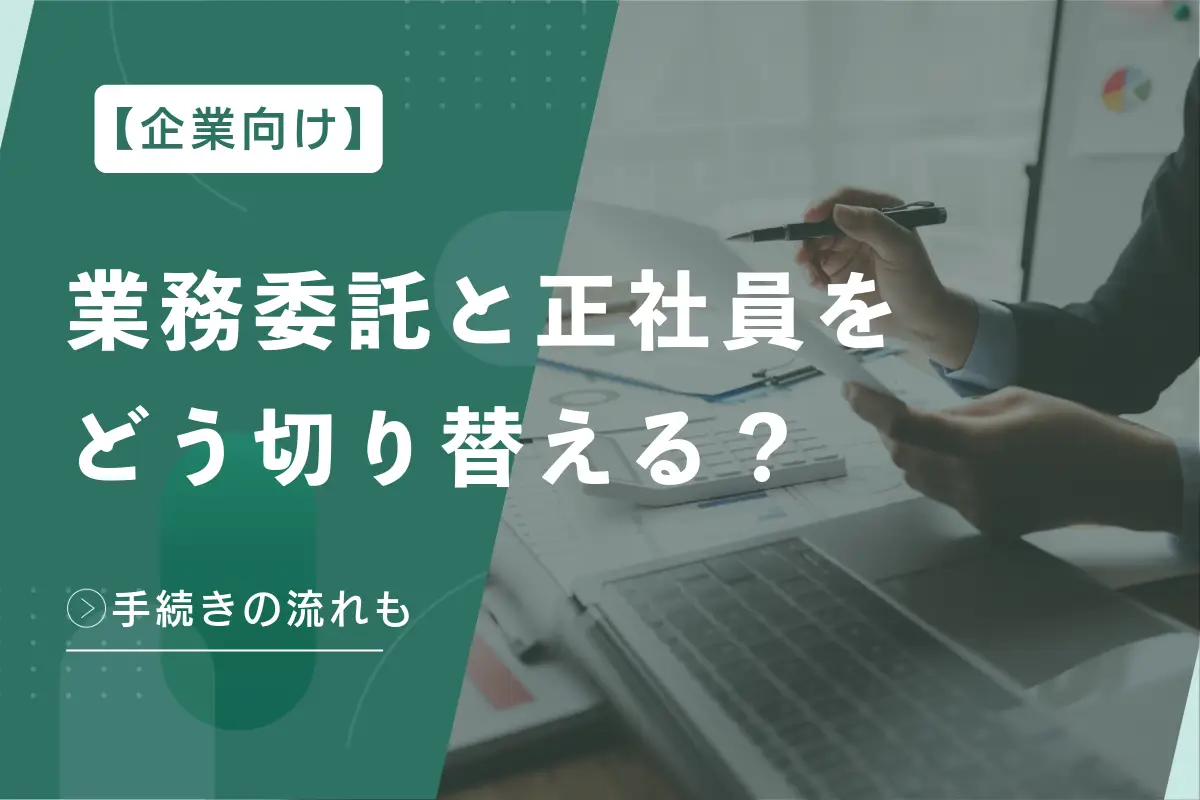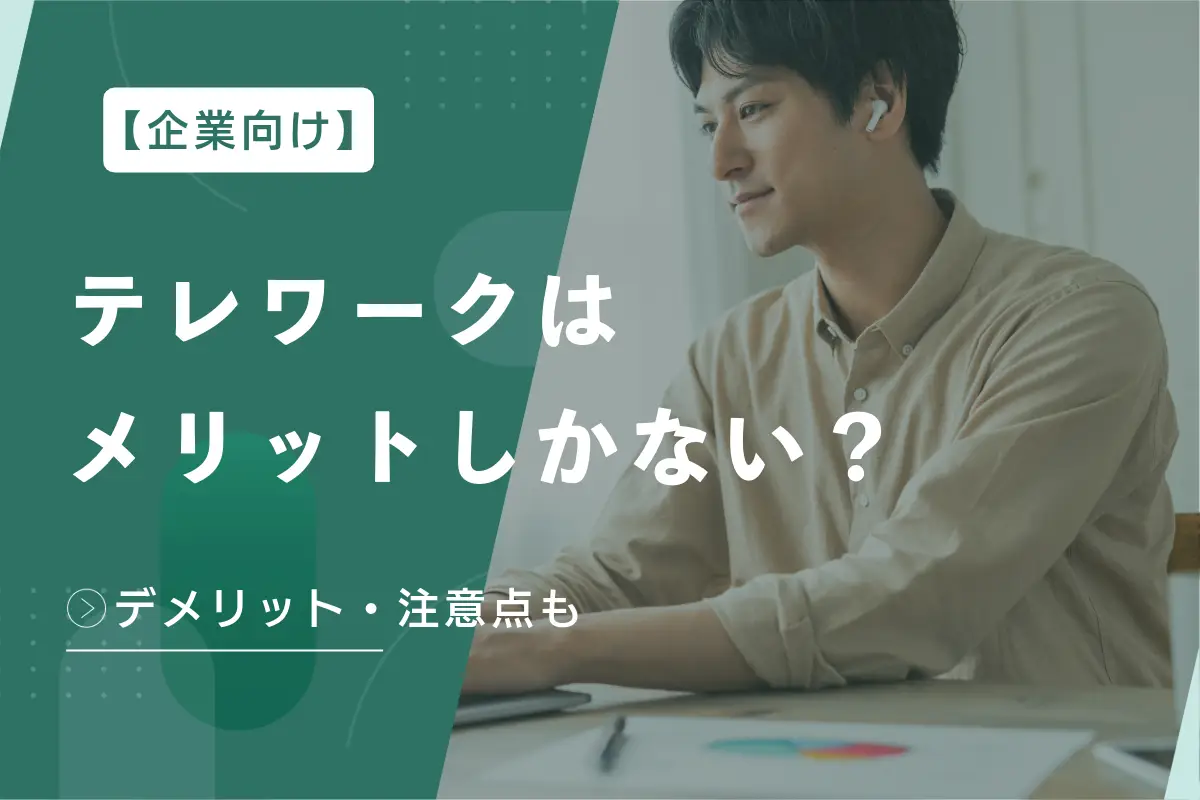「優秀な外部人材を正社員として迎え入れたい」「このまま正社員雇用を続けて大丈夫だろうか」と考えていませんか。近年、業績悪化による人件費圧縮や、優秀な外部人材の囲い込みを目的として、契約形態の見直しを検討する企業が増えています。業務委託と正社員は、契約内容や指揮命令などが大きく異なるため、切り替えには十分な注意が必要です。
本記事では、「業務委託から正社員」「正社員から業務委託」の切り替えについて解説していきます。それぞれの違いやメリット、手続きの流れ、注意点までわかりやすくまとめました。人材戦略のヒントとしてぜひご活用ください。
業務委託と正社員の違いとは?比較表で解説
業務委託と正社員は、契約形態が異なります。業務委託契約は成果物や業務の遂行に対して報酬を支払う契約であり、指揮命令の関係が原則ありません。一方、正社員は会社と雇用契約を結び、労働時間や業務指示に従う義務があります。以下の表では、両者の違いをまとめました。
項目 | 業務委託 | 正社員 |
契約形態 | 業務委託契約 (委任・準委任・請負) | 雇用契約 |
指揮命令関係 | 原則なし | あり |
勤務時間の拘束 | 原則なし | あり |
社会保険の適用 | なし(自分で加入) | あり(会社が負担) |
雇用調整の柔軟性 | 高い | 低い |
このように業務委託と正社員には明確な違いがあり、切り替えには慎重な判断が求められます。
業務委託から正社員への切り替えを企業が検討している背景
企業が業務委託者を正社員登用する背景には、深刻化する人材不足と採用手法の多様化が考えられます。厚生労働省は企業の人手不足を、少子高齢化の進行による働き手の不足を指摘。また人手不足は、特に「宿泊・飲食サービス」や「中小企業」において顕著だとしています。
出典:厚生労働省-令和6年度版 労働経済の分析-人手不足への対応-第2章 雇用情勢の動向
実際に転職市場では、リファラル採用(社員紹介)やアルムナイ採用(退職者再雇用)、副業者・フリーランスへの業務委託など、企業は多様な手段で人材獲得を進めています。こうした動きは、企業の柔軟な人材戦略の一環として、今後さらに広がっていくでしょう。
業務委託から正社員へ切り替える5つのメリット
ここでは、企業が業務委託から正社員に切り替えるメリットについて解説していきます。
優秀な人材を長期的に確保できる
自社業務の一部を担当している外部人材は、業務プロセスやカルチャーを既に理解しているため、スムーズに組織に溶け込むでしょう。こうした人材を正社員として迎えると、貴重なスキルやノウハウを活かした社内貢献が期待できます。
たとえば、開発や運用に関わるエンジニアを正社員化した結果、プロダクトの改善や、技術力の底上げに繋がった、というケースもあるほどです。プロジェクト単位の関係性では得にくい「継続的な貢献」が見込めるのは、正社員登用ならではのメリットと言えるでしょう。
組織の情報共有や内部統制がしやすくなる
正社員であれば、日常的に社内の業務フローやシステムへの関わりが増えます。企業のルールや管理体制への理解が進むことで、機密情報の共有や、チーム内での連携がしやすくなります。
また情報の取り扱いも、正社員であればアクセスできる範囲や責任を明確化しやすいため、セキュリティ面でも安心感が強いです。業務委託は制限が必要となるケースがありますが、正社員では社内ルールに従って柔軟に動ける分、組織内の情報管理や統制が容易となるでしょう。
人材の組織への帰属意識が高まる
業務委託者やフリーランス人材は、どうしても社外の立場にとどまりやすい傾向があります。正社員として迎え入れることで、企業文化や価値観に対する理解が深まり、自社への帰属意識が高まるでしょう。
日常業務への主体的な関わりに加え、社内イベントや制度設計など、企業内部の積極的な関与が期待できます。心理的な距離の縮まりにより、信頼関係をより深めながら業務を進められるでしょう。
指揮命令や業務指示がしやすくなる
業務委託契約では企業が外部人材に対し、原則、業務の進め方や勤務時間について細かい指示を出せません。
一方、正社員は労働契約のもと、企業の指揮命令下で働くため、業務内容の変更やスケジュール調整などスムーズに行えます。プロジェクトの進行やチーム連携が密になる場面では、正社員の方が柔軟かつ迅速に業務を操作できるため、企業としても管理がしやすくなるというメリットがあります。
労働契約で手続きや責任範囲が明確になる
正社員であれば、就業規則や労働契約に基づいた、明確な業務範囲と義務・権利を設定できます。これにより、トラブル発生時の対応方針が明確になり、法的なリスク管理もしやすくなります。
たとえば、残業・労働時間・有給取得といったルールを社内制度に従って運用できるため、人事管理上の透明性が向上します。業務委託では曖昧になりがちだった責任の所在も明らかとなることで、成果への評価基準が設定しやすくなるでしょう。
業務委託から正社員へ切り替える流れ
外部人材を正社員に切り替える際は、段階的な手続きが必要です。以下では、業務委託から正社員に切り替える流れについて紹介します。
1. 外部人材に正社員登用の意向を確認する
まず、業務委託契約を結んでいる人材に対し、「正社員になる意向があるか?」を確認しましょう。フリーランスとして働く理由は人それぞれで、「柔軟な働き方を重視したい」「特定の企業に縛られたくない」など、正社員登用を望まないケースも少なくありません。
そのため正社員登用の話を持ちかける際は、一方的な打診ではなく、本人のキャリアプランやライフスタイルへの考えを丁寧にヒアリングしましょう。給与水準・勤務場所・業務内容の変化など、登用後の待遇や条件も説明し、すれ違いが起きないよう配慮します。本人の意思を尊重しつつ、企業側の期待や今後の役割も共有しておきましょう。
2. 合意後、契約終了の手続きを実施する
正社員登用に双方の意思が一致したら、現在の業務委託契約を終了させる必要があります。契約終了の際は、業務委託契約書で定めた契約期間・解除条項などに従い、書面で手続きを完了させましょう。
さらにこのタイミングで、業務の引き継ぎや未払い報酬の精算も済ませておくとスムーズです。契約をクリアに終了させてから、正社員採用に進みましょう。
3. 正社員採用に関する手続きを行う
次に、正社員雇用で必要な手続きをします。以下の表では、手続きの流れをまとめました。
手続き項目 | 内容 |
1.正社員採用で必要な書類を発行する |
|
2.雇用契約書の締結 | 労働条件通知書と内容を一致させ、署名・押印または電子署名で正式的に契約する |
3.書類を提出してもらう |
|
4.入社日・出勤日の調整 | 本人と相談して入社日を決定、社内にも共有 |
5.社内通知・歓迎準備 | 配属部署やチームへの通知、準備物の手配 |
ここで気をつけたいのが、提出書類についてです。履歴書・職務経歴書は提出してもらい、他の正社員と同様の採用フローをとって手続きの平等性を担保しておきましょう。また評価・異動する際にも、履歴書・職務経歴書は経歴やスキルを把握する参考資料として活用できます。
4. 社会保険の切り替えや税務処理を進める
これまで業務委託を本業にしていたフリーランスは、一般的に国民健康保険や国民年金に加入しているでしょう。正社員雇用する場合、企業は健康保険や雇用保険などの社会保険へ切り替える必要があります。
また業務委託の場合、確定申告で所得税や消費税を納付していた手続きが、正社員雇用で給与からの天引きに変わります。その変更内容について外部人材にきちんと説明し、理解を得ることが重要です。
5. 社内オンボーディングを実施する
正社員登用後は、なるべく早く社内環境に馴染んでもらうオンボーディングが重要です。今後のビジョンや組織文化を共有し、企業理念への理解を深めてもらいましょう。配属先の部署紹介や業務フローの説明も丁寧に行うことで、新しい役割や責任を明確にできます。
また、社内システムやITツールの使い方をレクチャーし、新たに加わった社員が安心して働ける環境を整えておきましょう。チームメンバーとの交流会や、メンター制度の導入も効果的です。こうした取り組みにより、社員の定着率やモチベーションが向上します。
業務委託から正社員に切り替える際の注意点
以下では、業務委託から正社員に切り替える際の注意点について解説していきます。
雇用条件を明確にする
業務委託契約から雇用契約に切り替える際は、雇用条件の明確化が欠かせません。給与体系や勤務時間、評価制度など、正社員としての待遇や義務を提示しましょう。
これは双方の認識違いやトラブルの防止となり、新たな雇用関係を快くスタートさせるために重要です。契約時には就業規則を提示し、書面上での合意を得ましょう。
契約終了と新規契約の手続きを同時に進める
業務委託契約の終了と新規の雇用契約締結はタイムラグをできるだけなくし、同時進行で進めることをおすすめします。契約の空白期間が生じると、労務管理や給与支払いの面で混乱する可能性があります。
業務委託契約の終了日を設定し、「◯月◯日スタート」「翌月の初日から業務開始」など、正社員契約を開始するスケジュールを立てましょう。双方の合意を得た後、必要な書類や手続きも早めに準備し、抜け漏れのないよう進めていきます。
社内での役割や待遇の違いに配慮する
正社員になると、これまでの業務委託時とは異なる責任や役割が発生します。加えて、社内の他の正社員と待遇面で差異が生じないよう、既存社員のモチベーションに影響が出ないよう配慮が必要です。
たとえば、給与や昇給の基準、役割・ポジションについて説明しておきます。個別で話す時間を設け、疑問や不安を解消するサポートも効果的です。
正社員から業務委託契約への変更は可能?違法?
では逆に、「正社員から業務委託契約に切り替えるケースはあるのか?」という疑問を抱く方もいるかもしれません。実際、雇用契約から業務委託契約へ切り替えを行う企業は一定数おり、法律上も違法ではありません。
ただし、切り替えには慎重な対応が求められます。まず雇用契約を終了させるために、退職の手続きをする必要があります。
さらに、「偽装請負」とならないよう注意すべきです。偽装請負とは、実態は業務委託契約であるにもかかわらず、雇用契約(労働者)に近い働き方になっていることを指します。業務委託契約に切り替えた後、労働性が強い働き方が続く場合は、行政指導や法的リスクが発生する恐れがあるため気をつけましょう。
また、正社員から業務委託への切り替えは、本人の同意を得て進めることが大前提です。強制的な変更や説明不足は、労働紛争の原因にもなりかねません。正社員から業務委託契約への切り替えは法的には可能ですが、労務管理や契約内容の整備、丁寧な説明を十分に行い、リスクを回避しながら進めましょう。
正社員から業務委託へ切り替える5つのメリット
ここからは、正社員から業務委託へ切り替える5つのメリットについて解説します。
人件費を変動費扱いにできる
正社員雇用の場合、仕事の量に関係なく毎月決まった給料が発生します。業務委託契約に切り替えると、依頼した仕事に対して報酬を支払う形になるため、必要なときに必要な分だけの人件費となります。
そのため、「忙しい時期だけ人手を増やす」「事業の状況に合わせて人材コストを調整する」といったことが可能です。これにより、柔軟な経営体制が構築できます。
自社業務を熟知した人材に仕事を依頼できる
正社員から業務委託への切り替えは、すでに自社の課題や文化を熟知している人に、引き続き仕事を依頼できる点が大きなメリットです。業務の引き継ぎや、教育コストの大幅な削減が可能となります。
また信頼できる元社員に業務を委託することで、プロジェクトの精度やスピードを維持しつつ業務を進行できます。
組織のスリム化を図れる
正社員から業務委託への切り替えによって、企業は人件費・社会保険料・福利厚生といった固定的コストの圧縮が可能です。そのため組織全体のコスト構造を柔軟化でき、リスクの少ない経営体制に変えられます。
さらに、社員数が減ることで、階層や承認フローが簡略化され、意思決定のスピードが向上するでしょう。短期プロジェクトや新規事業など、スピード感が求められる場面では特に有効となります。
独立志向が高い人材の成長を後押しできる
「独立志向が高く、将来フリーランスとして活動したい」と考える社員にとって、業務委託契約への切り替えは朗報となる可能性があります。勤務経験がある企業との業務継続は、独立後の安定的な基盤となるでしょう。
また社員が業務委託者になると、複数のクライアントとの取引から、さらなるスキルアップが期待できます。自社の業務や文化に精通している人材を、外部パートナーとして新たに迎え入れると、これまでなかった提案や貢献が期待できます。
働き方の多様性をアピールできる
正社員から業務委託への切り替えによって、企業は多様な働き方を支援する体制を整えられます。
たとえば、子育てや介護などでフルタイム勤務が難しい人や、副業・独立を希望する人にとって、業務委託はライフスタイルに合わせた働き方を実現する選択肢となるでしょう。柔軟な契約形態の導入は、新たな人材活用のきっかけとなり、組織の機動力や対応力を向上させます。
こうした取り組みは、「多様性を重視する先進的な企業」としてのイメージアップにもなり、採用広報や企業ブランディングにも好影響です。
正社員から業務委託に切り替える流れ
雇用契約(正社員)から業務委託契約への切り替えは、労務管理や契約の観点からも慎重なステップが必要です。以下では、正社員から業務委託に切り替える流れとポイントを解説します。
1. 社員に意向を確認し、経緯を丁寧に説明する
会社の経営方針や事業構造の見直しにより、社員へ業務委託契約への移行を打診する際は、本人との十分な合意形成が不可欠です。
たとえばコスト削減のため、バックオフィス業務の一部を外注化することになった場合、社員にその経緯を伝える必要があります。具体的には、「これまでと同様の業務内容を、業務委託として継続していただけませんか?」といった形で提案します。
この時、業務委託契約後の働き方や報酬形態、社会保険の変更点など、具体的かつ丁寧な説明が欠かせません。本人が納得しないまま進めれば、不当解雇とみなされるリスクもあるため、合意を重視したプロセスが重要です。
2. 退職の手続きをする
会社都合で雇用契約から業務委託契約に切り替える場合、正社員としての契約を終了させる必要があるため、退職の手続きを進めます。具体的には契約終了の通知、最終勤務日の調整、給与精算といった処理をしていきましょう。不当解雇に該当しないよう、労働基準法に基づく解雇予告や理由の説明をしていきます。
次に、社員の反応を伺いつつ、業務委託契約を提案していきます。雇用形態の変更は、キャリアや生活に直結する大きな転機です。業務内容や報酬、稼働時間など、契約後の働き方を明確に伝え、双方が納得した上で進めることが重要です。加えて、業務委託に関する情報提供や説明など、サポートも継続しましょう。
3. 業務委託契約書を作成する
正社員の退職手続きが完了し、双方合意へとなった後、業務委託契約書の作成に進みます。業務内容や報酬、契約期間など、明確に提示していきましょう。
会社都合での切り替えの場合、トラブル防止のために「業務範囲」と「責任範囲」を細かく記載しておくと安心です。特に、正社員時代と業務内容が異なる部分の共有や、委託範囲の明確化は、互いの混乱を防ぐためにも有効となります。
さらに業務委託契約は、社会保険や労働法の適用外となるため、その点も本人に説明して理解を得ましょう。契約内容を詳細に詰めておくと、会社と候補者の双方が気持ちよく、新たな関係をスタートできます。
正社員から業務委託に切り替える際の注意点
正社員から業務委託に切り替える際は、以下の点に注意しましょう。
社会保険や報酬の仕組み、業務内容について説明する
正社員から業務委託に切り替わると、社会保険(健康保険・厚生年金保険など)から、個人で国民健康保険や国民年金に切り替える必要があります。このため、将来的な年金受給額や医療費負担の変化も事前に説明しておきましょう。
また報酬体系が固定給から業務委託料へと変わるため、源泉徴収の有無や、経費処理の方法についても伝えておきます。業務内容や責任範囲が変わる場合は、新たに期待する役割や成果物の内容を具体的に提示し、社員の誤解を防ぎましょう。加えて顧客情報や営業情報など、機密情報が外部に漏れないよう、情報の取り扱いについても説明しておくと安心です。
偽装請負に気をつける
業務委託契約であっても、実際の働き方が指揮命令下にある場合、偽装請負と認定されるリスクが高まります。
特に正社員として働いていた場合、つい業務を多量に依頼したくなるかもしれません。しかし、違法な偽装請負と認定されると行政指導や罰則の対象となります。事前に決めた委託範囲の作業を超える場合は、その都度、相談して業務内容を調整していきましょう。
既存社員のモチベーション低下を防ぐ
正社員の業務委託への切り替えは、本人だけでなく他の社員にも不安や動揺を与える可能性があります。特に「待遇の引き下げ」や「将来的な雇用不安」と受け止められないよう、経営層からの丁寧な説明や社内コミュニケーションの充実が重要です。
またキャリアパスの多様化や、働き方の選択肢としての切り替えであることを強調し、企業の支援体制や今後のフォローアップも伝えておきましょう。可能な限り、社員のモチベーション低下を防ぐ対応が求められます。
正社員・業務委託の切り替えに関するよくある質問3つ
ここでは、正社員・業務委託の切り替えに関するよくある質問についてまとめました。
1.正社員から業務委託への切り替えは、「クビ」扱いになるのか?
正社員から業務委託への切り替えは、基本的に一度正社員の雇用契約を終了してから、新たに業務委託契約を結ぶ形になります。このため、法律上は「解雇」に該当する可能性がありますが、必ずしも「クビ」扱いになるわけではありません。
重要なのは、会社と本人が合意した上で切り替えを進めることです。本人の同意がないにも関わらず、一方的に切り替えるとトラブルの原因になるため、丁寧に説明して納得を得ましょう。
2.同じ会社で「正社員から業務委託」「業務委託から正社員」に切り替えるのは法的に問題ない?
「正社員から業務委託」あるいは「業務委託から正社員」への切り替えは、法律上は問題ありません。ただしそれぞれの契約を、以下のように終了・開始する手続きをきちんと踏みましょう。
- 「正社員から業務委託」に切り替える場合…雇用契約を一度終了し、改めて業務委託契約を結ぶ
- 「業務委託から正社員」に切り替える場合…委託契約の終了手続きと並行し、正社員雇用の手続きをする
いずれの場合も「契約の継続」ではなく、「新たな契約形態として再スタートする」という意識が重要です。責任範囲・報酬体系・勤務時間などの条件を明確にし、トラブルを未然に防ぎましょう。
3.会社都合での「正社員から業務委託」への切り替えは、問題にならない?
会社都合で正社員から業務委託に切り替えること自体は、法律で明確に禁じられているわけではありません。しかし、実質的に「退職の強要」や「不当解雇」に該当するような進め方をすると、法的トラブルになる可能性があります。
たとえば、社員が切り替えに同意していないにもかかわらず、「一方的に退職を迫る」「業務委託でないと今後は働けない」とした場合、労働基準法に違反する恐れがあります。
また、本人の合意がないまま雇用契約を終了させることは「解雇」とみなされるため、解雇予告や正当な理由が必要です。会社都合での切り替えを円滑に進めるには、以下のような対応が重要となります。
- 十分な説明と話し合いを行い、本人の納得と合意を得る
- 切り替えの理由や背景を説明する
- 退職手続きと新たな契約手続きを明確に分けて実施する
- 切り替え後の業務内容や報酬体系、責任範囲を契約書で明文化する
社員の理解と信頼を得ながら、適切にプロセスを踏んでいきましょう。
業務委託から正社員への切り替えは、転職エージェントの『WorkshipCAREER』におまかせ!
本記事では、業務委託と正社員の違いや、「業務委託から正社員」「正社員から業務委託」の切り替えを検討するメリットなど、解説してきました。
業務委託から正社員への転換は、「即戦力人材の長期確保が可能」といった良さがあります。しかし、「フリーランスから正社員化する採用手法を取り入れたいけれど、どのように進めればいいかわからない」と戸惑うこともあるでしょう。そんなときは、『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』におまかせください。
Workship CAREERでは、ITエンジニアやクリエイターを中心に、多様なスキルを持つ優秀な人材を多数保有しています。業務委託から正社員への切り替えや、採用後のフォローまで幅広くサポートいたします。
Workship CAREERの特長
- トランジション採用の導入:業務委託契約からスタートし、その後正社員登用への切り替えをサポートいたします。
- 豊富な人材データベース:エンジニア、デザイナー、PMなど、約5万人以上のフリーランスネットワークから、企業のニーズに合った候補者をご紹介いたします。
- 人事のプロが採用から育成まで一貫して伴走:貴社の人事課題をヒアリングした上でトータルに解決いたします。
「採用のミスマッチをなくしたい」「事業成長に貢献する人材を確保したい」という企業様は、Workship CAREERにご相談ください。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
- Workship CAREERのサービス内容
- ご契約の流れ
- 取引実績
- 関連サービス

リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェント「Workship CAREER」の編集部です。採用に役立つ情報を発信していきます。