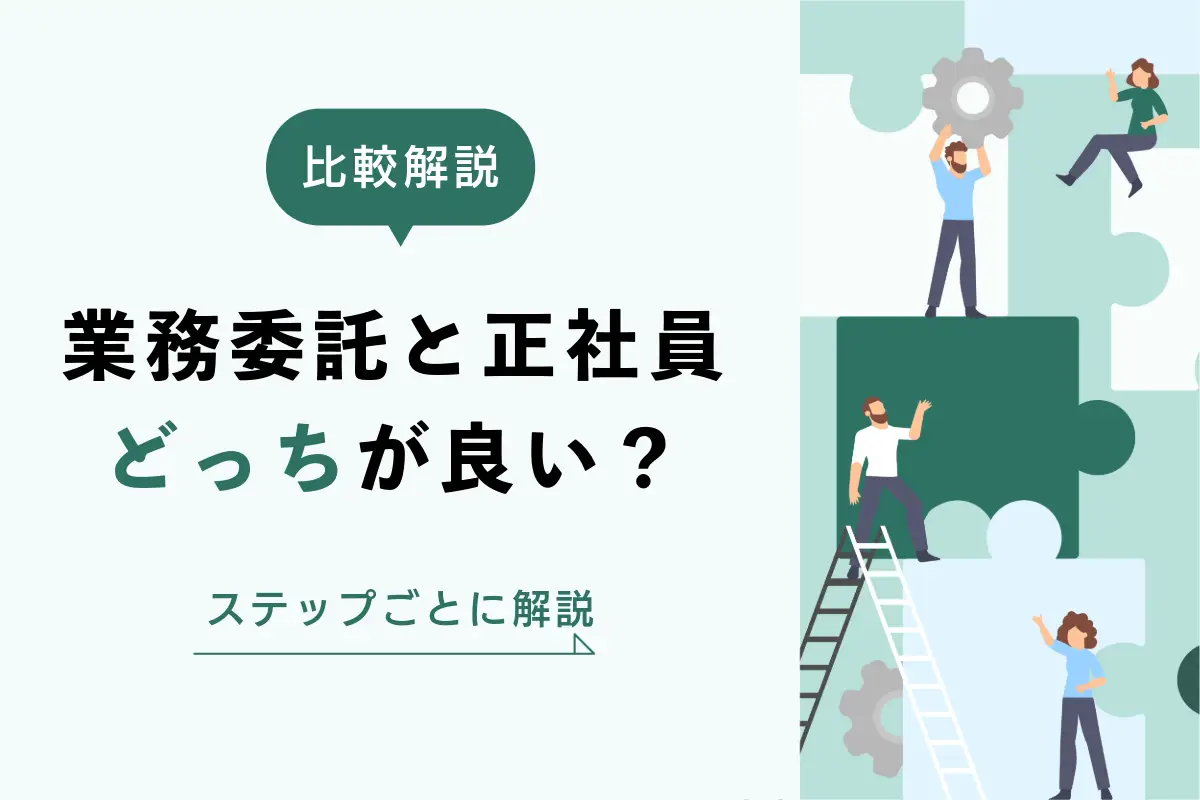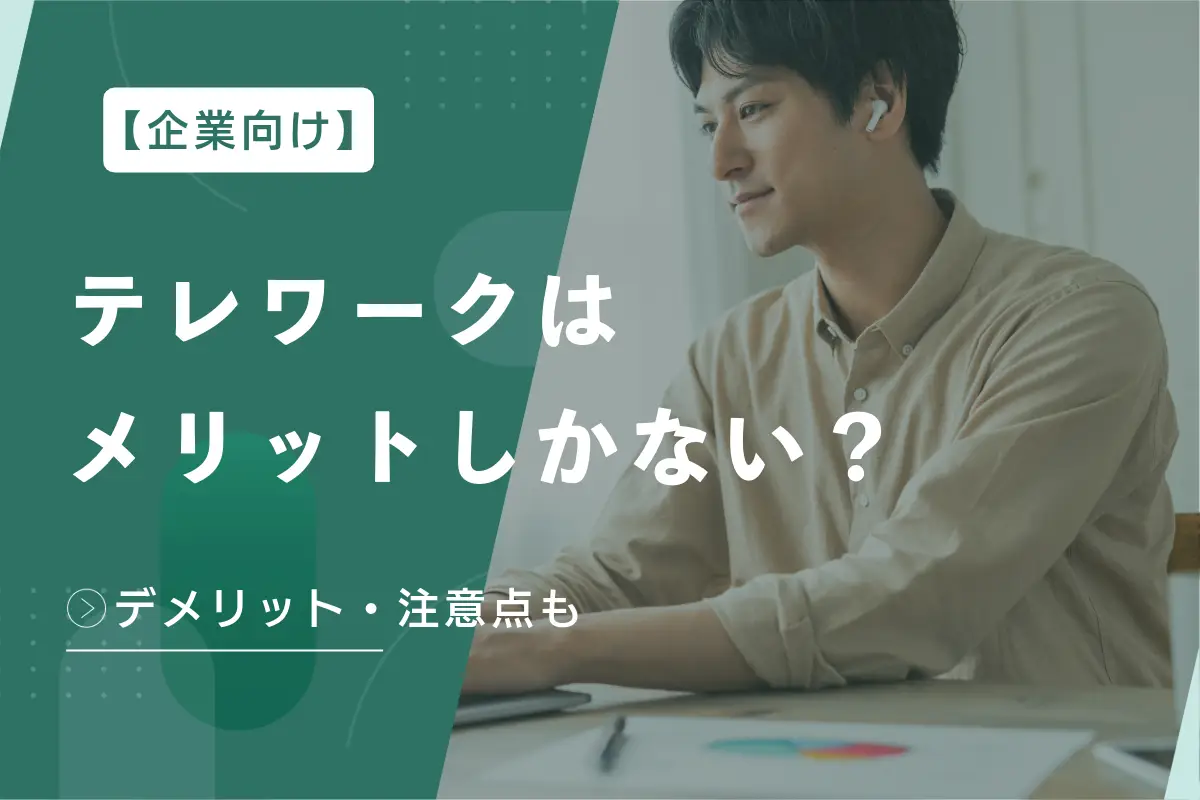働き方の多様化や人材市場の動きを受け、これまで正社員採用が中心だった企業の多くが業務委託を検討しています。またすでにフリーランスと協業している場合、「この人材を正社員として迎えたい」と感じるときがあるでしょう。
業務委託と正社員の違いや、正社員転換の流れを把握しておかなければ、適切な人材活用ができず、組織運営に支障をきたす恐れがあります。
そこで本記事では、業務委託と正社員の違いやメリット・デメリットを比較。さらに、業務委託から正社員登用する際の具体的なステップや注意点まで網羅的に解説していきます。人材戦略の見直しや、採用手法の多様化を考えている企業はぜひ参考にしてみてください。
業務委託契約と雇用契約(正社員)の違い
業務委託契約と雇用契約(正社員)は、働き方や報酬形態が異なるため注意が必要です。業務委託契約では、成果物の提供や業務の遂行に対し、外部人材に報酬を支払います。一方、正社員は働く時間や業務内容に応じて企業が給与を支給します。
どちらにもメリット・デメリットがあり、自社のニーズや求める人材の役割に応じて適切な契約形態を選んでいきましょう。下の表では、両者の違いをまとめました。
項目 | 業務委託契約 | 雇用契約(正社員) |
法律上の扱い | 個人事業主(フリーランス) | 会社に雇われた労働者 |
指揮命令 | 原則なし (業務内容に基づく契約) | 会社の指示命令に従う義務がある |
働く時間・ 場所 | 基本的に自由 | 特定の時間・場所での勤務が多い |
報酬・給与の出し方 | 請負・委任・準委任 (成果物や業務遂行に対する報酬) | 毎月の固定給 (時間や日数に応じて支給) |
社会保険 | 原則、自己負担 (国保・国民年金に加入) | 会社が一部負担 (健康保険・厚生年金・雇用保険など) |
福利厚生 | 原則なし | 有給・育休など、会社規定により適用あり |
契約の柔軟さ | 契約内容を調整しやすい | 雇用継続が前提 |
安定性 | 契約期間が終われば終了 | 原則、長期雇用が前提 |
以下の章からは、業務委託と正社員のメリット・デメリットを紹介していきます。
業務委託と正社員雇用のメリット
業務委託と正社員は、どちらにも独自のメリットがあります。
業務委託契約のメリット | 正社員雇用のメリット |
|
|
それぞれの良さについて具体的に解説していきます。
【業務委託】必要な時に専門人材へ仕事を依頼できる
業務委託の場合、リソース不足で人材を補充したいときや、特定スキルが必要な場合、すぐに専門人材へ仕事を依頼できる点がメリットです。
たとえば、「短期的に動画編集を依頼したい」という場合、動画制作のプロによって対応してもらえます。採用にかかる手間やコストを抑えつつ、良質なアウトプットが受けられる点は、業務委託ならではの大きな利点といえるでしょう。
【業務委託】コストの柔軟性が高い
業務委託契約は、必要な業務に対して報酬を支払うため、人件費を変動扱いにできます。そのため、予算や業務量に応じたコスト設計が可能です。
たとえば、「繁忙期だけ広告運用やデザイン制作を専門家に依頼する」「短期間でスキルの高い人材を活用する」といったこともできます。状況に応じて必要な時期だけに仕事を頼めるため、先行きが読めない場合もコストの調整をしつつ業務を進められるでしょう。
【業務委託】社内にないスキルを迅速に補える
急成長中の企業や新規事業では、「社内にまだ存在しないスキル」が必要になる場面があるでしょう。業務委託なら社員雇用せず、社内に必要な即戦力人材に業務を依頼できます。
たとえば、「Web3や生成AIといった最新技術に精通した人材」「海外マーケティングに強いコンサルタント」など、ニッチでハイレベルな専門性を持つ人材に仕事を任せられるでしょう。優秀な人材をスピーディーに確保するには、フリーランス専門エージェントやマッチングサイトの活用が効果的です。
また昨今、業務委託人材の活用が進んでおり、多くの企業がその良さを体感しています。パーソルキャリア株式会社の調査によれば、副業人材を活用する管理職の9割以上が、「副業人材が会社に良い影響を与える」と回答。「社員の生産性向上に繋がった」「既存ビジネスの課題解決が進んだ」といった評価もあります。上記の点から、業務委託は社内の働き方や、プロジェクトの推進にも波及効果をもたらすことが期待できます。
【正社員】長期的な人材育成・組織定着が図れる
正社員の場合、自社の業務や文化に馴染みつつ、時間をかけて人材育成できる点が大きなメリットです。長期勤務が前提であるため信頼関係を築きやすく、将来的に会社の中核を担う存在へと成長してもらえるでしょう。
そのため「新卒や若手社員を一から育てたい」「企業カルチャーを共有して組織を強化させたい」と考える企業には、正社員雇用がマッチします。
【正社員】プロジェクト間の異動や社内連携がスムーズ
正社員は、部署間の異動やチーム編成もスムーズです。新しいプロジェクトのスタートとともに、メンバー体制の構築を円滑に進められるでしょう。
また、社内の業務フローやナレッジにも精通しているため、他部署や複数業務との連携・引き継ぎがしやすいです。組織の中で臨機応変な対応がとれる点は、正社員の良さとなります。
【正社員】組織に対する帰属意識が高い
企業理念やミッションに共感しながら働くため、正社員は主体的に仕事する傾向があります。その結果、会社の文化づくりや、制度設計への積極的な関与が期待できます。
たとえば、新制度の提案や後輩への指導などは、企業を熟知した正社員だからこそリーダーシップが発揮しやすい業務です。また長期勤務によって社員同士の絆が深まることで、組織やチームが活性化していくでしょう。
業務委託と正社員雇用のデメリット
次に、業務委託と正社員雇用のデメリットについて紹介します。
業務委託契約のデメリット | 正社員雇用のデメリット |
|
|
【業務委託】業務範囲が限定的になりがち
業務委託契約では、委託業務の範囲を契約書に明記する必要があります。そのため原則、契約書に記載された業務以外の作業は、本人の同意なく依頼することはできません。
たとえばSNS運用を任せたフリーランスに対し、LP制作も依頼したい場合、新たに契約内容を見直す必要があります。突発的な業務依頼や、優先度の変更依頼が難しい場合があるため、業務委託は臨機応変に対応しにくいと感じるかもしれません。従って適宜、請負契約から準委任契約に移行するなど、契約形態の見直しを図るといいでしょう。
【業務委託】情報漏えいや法的リスクの管理が必要
外部人材との契約である以上、業務委託では情報管理のリスクに留意しましょう。たとえば、顧客情報や未公開内容にアクセスする場合、その取り扱いルールの伝達や、秘密保持契約(NDA)の締結を実行しましょう。
また、業務の指示や進行の仕方によって「実態が雇用に近い」と判断された場合、偽装請負に該当する恐れがあります。そのため、法令を遵守した管理体制や情報漏えいの防止策をとっておきましょう。
【業務委託】ナレッジやノウハウが社内に蓄積されにくい
外部人材に依頼して成果を上げた場合、その過程や工夫が社内で共有されないまま契約終了となるケースがあります。
たとえば広告運用をフリーランスに委託した場合、成果の出し方や効果的な改善施策といった知見を共有しておかなければ、社内での再現性が確保できません。「外部人材が変わるたびに一から立ち上げ」となると、長期的に知識の資産化が難しくなります。
そのため、成果やプロセスを自社のナレッジとして蓄積されるよう、工夫が求められます。具体的には、外部人材と共有する業務マニュアルや進行管理シート、成果報告テンプレートなどを整備し、プロジェクトの過程や判断基準を見える化しておきしょう。定期的な振り返りやナレッジ共有会を実施するのも効果的です。
【正社員】人件費リスクが大きい
正社員を雇用すると、業務の有無にかかわらず固定的な給与や社会保険料の支払いが発生します。景気が不安定な時期や、プロジェクトの増減が激しい企業は、この固定費が経営上の重荷となることもあるでしょう。
特にスタートアップ企業では、「採用したものの事業方針が変わって役割がなくなった」といった事態も起こりうるため、採用前の見極めが重要です。
【正社員】採用・育成に時間がかかる
正社員採用には、「募集・面接・内定・入社」と多くのステップがあり、場合によっては数カ月を要します。企業文化の理解や業務習得も一定期間必要となるため、即戦力としての活躍には時間がかかるでしょう。
正社員は「すぐに人手が欲しい」「短期間で成果を出したい」といった企業のニーズに対応しにくく、焦って採用するとミスマッチが生じます。そのため、フリーランスから正社員化するトランジション採用を導入するといった柔軟な対応が求められるでしょう。
【正社員】早期解雇や人事配置をすぐにはできない
正社員は労働法で保護されている立場です。そのため会社都合による一方的な解雇や、勝手な人員の配置転換・降格が禁止されています。特に解雇は、客観的に合理的な理由や、社会通念上の相当性が求められ、不当と判断されればトラブルや訴訟に発展するリスクがあります。
また人手不足の部署に異動させたい場合、本人の同意や希望の調整を伺う必要があるため、必ずしもスムーズに配置転換できません。変化の激しい事業環境では、こういった柔軟性の欠如が、大きな経営課題となる可能性があります。人事戦略を立てる際は、将来的な組織変更や縮小リスクを見越した適切な人員配置が鍵となるでしょう。
業務委託と正社員、どっちがいい?目的別に比較
「業務委託と正社員、どちらが自社に適しているか?」という疑問に対し、ここでは、目的別に両者を比較していきます。
業務委託が向いているケース | 正社員が向いているケース |
|
|
柔軟性・スピード重視なら業務委託
短期間で成果が求められるプロジェクトや、急な業務の増加に対応したい場合は、業務委託が有効です。採用活動の手間や教育コストが不要なため、スピーディーに即戦力を確保できます。
特にスタートアップや小規模チーム、変化の早い現場ではそのメリットを大きく感じられるでしょう。必要なときに必要なスキルを持つ人材と連携できる業務委託は、組織に高い柔軟性をもたらします。
長期的な戦力化なら正社員
「企業の中核を担う人材を育てたい」「長期的に事業を支える組織力を強化したい」と考えるなら、正社員雇用が最適です。時間をかけた人材育成により、業務理解や企業文化への適応が進み、深い信頼関係が築けるでしょう。
さらに社内のノウハウが蓄積されやすいため、将来的なマネジメント層へのステップアップも期待できます。人材の定着とともに組織全体の安定性を目指す場合は、正社員が有効です。
採用のミスマッチを防ぎたいならトランジション採用が有効
人材との相性を重視したいなら、業務委託から正社員登用へとつなげる「トランジション採用」がおすすめです。一定期間、業務委託として「スキル・働き方・人間性」を見極めた上で正社員登用を判断できるため、雇用後のミスマッチを大きく減らせます。
求職者側にとっても、企業のカルチャーや業務内容を理解した上で正社員になるかを選べるため、双方にとって納得度の高い採用が実現できます。採用の成功率を高める新しいアプローチとして効果的です。
フリーランス(業務委託)から正社員に転換する5つのステップ
フリーランスに業務を委託している企業の中には、「いきなり正社員雇用を打診するのは不安」と感じることもあるでしょう。そこでここからは、フリーランス人材をスムーズに正社員転換する5つのステップを紹介します。
ステップ1. 業務委託契約締結の段階で正社員登用の可能性を伝える
まず、業務委託契約を結ぶ初期段階で、将来的な正社員登用の可能性を提示しておきましょう。
たとえば契約前の説明時には、「今回の業務はまず業務委託でお願いしたいのですが、パフォーマンスや相性がよければ、正社員としてお迎えする可能性もあります」と伝えるといいでしょう。契約書や覚書には、「双方の合意と業務成果に応じ、将来的に正社員雇用の打診を行う場合があります」と記載します。
このように最初から正社員登用の可能性がわかれば、相手も将来の選択肢として意識するようになり、仕事へのモチベーションが高まります。また正社員登用の旨を知らせておくと、企業側も「ミスマッチを避ける見極めの期間」として業務委託期間を有効活用できます。
ステップ2. 実績とカルチャーフィットを見極める
業務委託での稼働が始まったら、成果物の質だけでなく、働き方やチームとの相性(カルチャーフィット)も評価しましょう。以下では、外部人材との相性を確認したい場合に活用できる、チェックポイントの例をまとめました。
【チェックポイントの例】
- 期限内に成果を納品しているか?
- 報連相が適切にできているか?
- 社内ツールやルールに柔軟に対応できているか?
- チームメンバーとの協働にストレスがないか?
また、Slackや会議でのやり取りや、担当マネージャー・周囲のメンバーからのフィードバックを収集するのも効果的です。月次で簡易的な評価シートをつけておくと、情報が可視化されて評価しやすいでしょう。正社員登用の場合、実績だけでなく「この人と長く働きたいか」という観点が重要です。
ステップ3. タイミングを見て打診し、外部人材の意向を確認する
カルチャーがフィットして成果も出ていると感じたら、フリーランス側の意向を丁寧にヒアリングします。打診のタイミングは、3ヶ月・6ヶ月といった節目や、プロジェクトの終了・区切りがついた頃、チームの体制変更や中長期戦略の変更時がおすすめです。 以下のように声かけするといいでしょう。
- 「実は社内で、〜さんを正社員としてお迎えできないかという話が出ていまして…ご興味ありますか?」
- 「長期で一緒に働くイメージを持っていて、正社員でのご相談をさせていただけたらと考えています」
相手のライフスタイルや希望を尊重しつつ、前向きなスタンスで意向を聞き出しましょう。
ステップ4. 正社員雇用の条件を丁寧に提示して調整する
興味を示してもらえたら、条件をすり合わせる段階に入ります。不安を取り除きつつ、明確かつ丁寧に伝えていきましょう。具体的には、以下のような点を明示していきます。
- 年収(基本給+賞与)
- 勤務形態(出社・リモート・フレックスタイムなど)
- 業務内容の変更有無
- 社内制度(有休、福利厚生、評価制度など)
上記の点を提示する際は、「現状の働き方とギャップが少ない」「柔軟な働き方を継続できる」といった、相手の不安要素を先回りして説明するとより効果的です。
ステップ5. 社内の労務手続きと体制づくりを整備する
雇用に合意が取れたら、雇用契約書の作成や社会保険の加入といった労務手続きや、受け入れ体制の整備に進みます。業務フローが円滑に進むよう、適宜、人事労務管理システムを活用するといいでしょう。
また、入社初日からスムーズに業務へ着手できるよう、労務チームや現場マネージャーとの連携も重要です。入社後はオンボーディングを実施し、新入社員の不安を軽減させ早期離脱を防ぎます。加えてこれまで委託していた業務の引き継ぎを行い、正社員としての目標設定を促すと、企業への帰属意識がより高まるでしょう。
業務委託から正社員への切り替えに最適なタイミング5つ
以下では、企業が外部人材を正社員へ切り替えるのに最適なタイミングについて紹介します。
1. 契約期間が長期化してきたとき
「業務委託契約が1年以上継続」といった長期的な関係の場合、正社員登用を検討するタイミングとして最適です。仕事の依頼が継続している、ということは、スキルや信頼性が社内で一定以上評価されている証でもあります。
また外部人材も、「将来の安定やキャリアを見据えて働き方を見直したい」と思っているかもしれません。正社員化の相談では、本人のキャリアビジョンやライフスタイルを確認した上で打診してみましょう。一方的な提案にならないよう、相互の意向をすり合わせる姿勢が大切です。
2. 社内メンバーとの協働がスムーズになってきたとき
業務委託の人材が社内メンバーと円滑に連携し、チームの一員として自然に機能しているようであれば、正社員登用を考えてもいいでしょう。業務の理解度が高まり、報連相やプロジェクト進行もスムーズなら、今後さらに社内での活躍が期待できます。
また、フリーランスの多くは、働き方の自由度に魅力を感じています。そのため正社員化を打診する際は、無理に雇用形態を変えるのではなく、外部人材の意向を聞きながら双方納得のいく形で切り替えを進めていきましょう。
3. 本人から正社員化の希望が出たとき
「もっと安定的に働きたい」「正社員として勤務したい」のように、外部人材から意思表示がある場合、正社員化の好機となります。前向きな希望であれば、受け入れがスムーズです。
ただし、いくら本人が希望していても、明らかに自社のカルチャーや働き方にミスマッチである場合は、無理に正社員登用すべきではありません。相性が合わないまま雇用を切り替えると双方にとってストレスとなり、早期退職に繋がる恐れがあります。冷静な見極めと対話を行い、正社員化を検討しましょう。
4. 業務領域が拡大し、裁量や責任が増えてきたとき
外部人材の担当領域が広がり、高い裁量や責任が増えてきた場合、正社員登用を検討すべき時期といえるでしょう。業務の中心的存在になりつつあるなら、安定した雇用関係を築くことで、さらなる貢献を引き出せる可能性があります。
正社員化の希望を聞き出す際は、本人のキャリアプランや働き方の希望をヒアリングします。一方的な判断で雇用形態を変えると、モチベーションの低下やミスマッチの原因になるため、慎重にコミュニケーションをとっていきましょう。
5. 戦力化が見込め、今後の中核人材として期待できるとき
業務委託としての実績が高く、将来的に自社の中核を担えるポテンシャルを感じれば、正社員登用を前向きに検討した方がいいでしょう。
たとえば事業成長に不可欠なスキルの保有や、新規プロジェクトをリードする姿が見られたとき、正社員化を打診していきます。
ただし正社員登用を進める際は、「なぜその人材を中核として迎えたいのか」を社内で明確にし、本人と共有しておくことが欠かせません。仮に適性が一致しない場合、無理に正社員化せず、別の形で関係を継続するといった柔軟な判断も重要です。
業務委託から正社員登用する際の注意点
以下では、業務委託から正社員登用する際の注意点について解説していきます。
雇用契約に切り替え、法令に沿った手続きをする
業務委託から正社員への切り替えでは、契約形態や法令に従って手続きを適切に進めていきましょう。以下では、手続きの内容や必要な対応についてまとめました。
手続き内容 | 必要な対応 |
契約形態の変更 | 業務委託契約( 請負・委任・準委任)→ 雇用契約への切り替え |
社会保険の加入 | 国保の脱退→健康保険・厚生年金保険・雇用保険の手続き |
就業規則の適用 | 勤務時間・給与・休暇等の規定確認 |
給与体系の変更 | 月給制または年俸制への移行、賞与等の設定 |
労働法遵守 | 労働基準法、労働契約法に基づいた契約書の作成 |
業務委託から正社員に切り替える場合、契約内容を法律に則った形に変えていきましょう。
正社員の場合、労働基準法や労働契約法に基づいて記載していきます。業務委託時には自己負担で加入していた保険も、正社員登用後は企業が一定額負担する形に変更します。業務委託契約時での業務内容が変わるため、事前に説明して同意を得ておきましょう。
カルチャーフィットやチームの適応性を確認しておく
スキルや実績が豊富でも、自社の価値観や働き方と合わなければ、正社員登用後に摩擦が生じます。特にベンチャー企業では、個人の裁量やスピード感、チームとの密な連携が欠かせないでしょう。カルチャーの不一致は離職の原因となり、生産性の低下となりかねません。そのため、価値観や行動スタイルの見極めが重要です。たとえば、以下のような点をチェックしましょう。
- 【報連相や相談のタイミング】自発的に動けるタイプか、指示待ち型か
- 【コミュニケーションのスタイル】オープンで積極的か、控えめで慎重か
- 【柔軟性】変化の多い環境でも適応できるか
- 【価値観の一致度】会社のミッション・ビジョンへの共感があるか
- 【チームへの溶け込み具合】雑談やミーティングなどで自然に会話できているか
また登用を急ぐあまり、「スキルがあるからOK」と判断すると、後に文化的なミスマッチが発生する恐れがあります。
できれば業務委託期間中に、チーム内のイベントやミーティングに積極的に巻き込み、内面的な相性を確認しておくと安心です。カルチャーフィットは「合う・合わない」ではなく、「歩み寄れるか」「成長を共にできるか」を基準に見極めましょう。
報酬体系や福利厚生といった労働条件の違いを説明する
業務委託から正社員に転換する際、報酬体系や福利厚生の違いを事前に伝えましょう。業務委託は基本的に、成果物や時間単価に基づく報酬で、月単位やプロジェクト単位で変動します。正社員は固定給が基本で、年俸制や月給制、ボーナスが含まれる形です。
福利厚生では、業務委託の場合、基本的に社会保険が自己負担となります。正社員は企業が社会保険を負担し、年次有給休暇や育休・産休、通勤手当などが提供される、といった違いがあります。これらの相違点を理解してもらい、正社員登用後で変わる点についても事前に説明しましょう。
正社員登用後の役割やキャリアパスを伝えておく
業務委託から正社員に転換する際、正社員登用後の役割やキャリアパスも伝えておきましょう。業務委託では主にプロジェクト単位で業務を行うため、正社員登用された際に期待される役割や責任の範囲、成長の機会が変わるケースがあります。
昇進やスキルアップなど、具体的なキャリアプランの提示は、入社後の目標設定にも役立ちます。社員としての期待値や長期的な展望、役割を伝え、新入社員の意欲を向上させていきましょう。
業務委託と正社員に関するよくある質問3つ
ここでは、業務委託と正社員に関するよくある質問3つを紹介します。
業務委託は「やめたほうがいい」と言われているのはなぜ?
業務委託が「やめたほうがいい」と言われる理由は、契約の不安定さや福利厚生の欠如が挙げられます。業務委託は収入が不安定で、社会保険や有給休暇などの福利厚生がないことが問題視されています。
また、税務面や契約内容に関する知識が求められ、フリーランスとしての独立性が高い分、個人でのリスク管理が必要になります。これらの理由から、安定した収入や福利厚生を求める人には不向きとされ、正社員を選択するケースに移行する場合があるということです。
業務委託で働いていた人材を正社員化する際、面接は必要ですか?
正社員登用の際も、面接や書類提出といった正式な選考プロセスは行うべきです。すでに協業している人材であっても、正社員としての役割や長期的なキャリアビジョンがマッチしているかを確認するため、改めて面談を実施しましょう。
特に報酬・勤務条件の変更や、責任範囲の明確化など、認識のズレを防ぐ意味でも丁寧な対話が不可欠です。
業務委託と正社員の掛け持ちは可能ですか?
同じ企業で「業務委託契約」と「正社員契約」の同時契約は、基本的に避けるべきです。理由は、実態が雇用であれば法律上「雇用契約」とみなされるためです。たとえ業務委託と称していても、指揮命令下で働いていれば雇用と判断され、二重契約による税務・社会保険の混乱や労務リスクが発生します。
企業として、どうしても両立が必要な場合でも「一時的な副業」といった契約範囲を明確にし、できるだけ契約形態を一本化することが望ましいでしょう。「自社で正社員」「他社で業務委託」といった掛け持ちは条件付きで可能です。ポイントは以下の通りです。
- 自社の就業規則で副業が許可されているか?
- 他社の業務が競業・利益相反に当たらないか?
- 機密保持や就業時間との両立が可能か?
副業を希望する社員には事前申告を促し、業務への影響を考慮しながら適切に管理していきましょう。
業務委託から正社員雇用に転換するなら、転職エージェントの『Workship CAREER』におまかせ!
本記事では、業務委託と正社員の違いや、正社員転換のステップなど解説してきました。フリーランスや副業人材を正社員として採用する「トランジション採用」は、即戦力人材を確保しつつ、採用のミスマッチを防ぐ有効な手段です。
しかし正社員化には、労務手続きや条件調整など、さまざまな課題が伴います。そんなとき頼れるのが、IT・DX業界専門の転職エージェント「Workship CAREER(ワークシップキャリア)」です。
Workship CAREERの特長
- 豊富な人材データベース:エンジニア、デザイナー、PMなど、約5万人以上のフリーランスネットワークから、企業のニーズに合った候補者を紹介いたします。
- トランジション採用の支援:業務委託契約から正社員登用への切り替えを、双方合意のもとサポート。専門スタッフが契約時の切り替えや手続きを支援いたします。
- 人事のプロが採用から育成まで一貫して伴走:定例会議や週1~3日での対応から、貴社の人事課題をトータルに解決。
Workship CAREERでは無料相談が可能です。貴社の採用課題や悩みをヒアリングし、最適な人材をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。
- Workship CAREERのサービス内容
- ご契約の流れ
- 取引実績
- 関連サービス

リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェント「Workship CAREER」の編集部です。採用に役立つ情報を発信していきます。