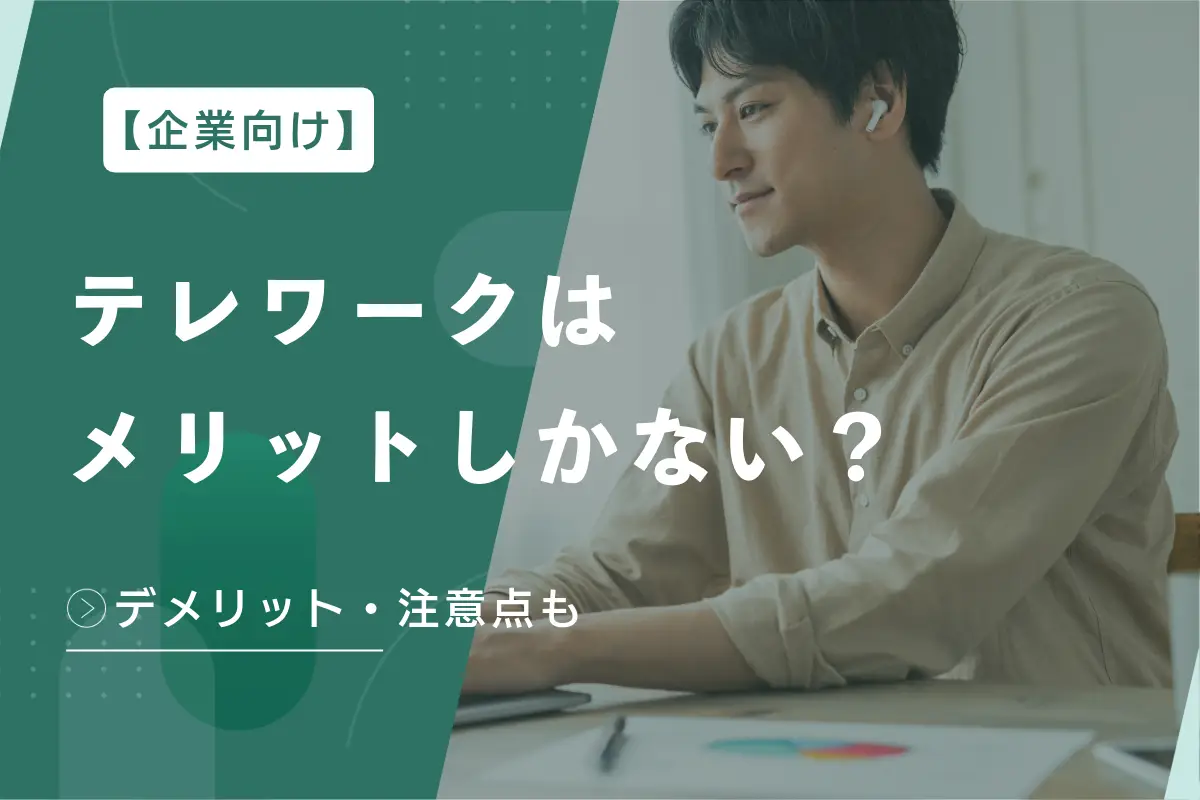正社員と契約社員、どちらの雇用形態で採用すべきか悩む企業も多いでしょう。正社員は「無期雇用」、契約社員は「有期雇用」という明確な違いがあるため、ぞれぞれのメリット・デメリットを把握した上で雇用形態を決定していくことをおすすめします。
本記事では、正社員と契約社員の違いについて深掘りしつつ、契約社員から正社員登用する際のステップや注意点など幅広く解説します。
契約社員とは?
契約社員とは、一定の契約期間を定めて契約を結ぶ雇用形態のことです。一般的には「有期雇用契約」と呼ばれ、「1年」「半年」など、具体的な期間を設定して採用します。契約期間満了後は、契約更新・終了するかを企業と労働者の双方で判断していきます。
契約社員の場合、必要な期間・業務範囲に限定して人材を確保できるため、正社員採用よりもコストを抑えられます。また、適性やスキルを見極めてから正社員登用を検討する「トライアル的な期間」として位置付けられる点もメリットです。
正社員と契約社員の違い
正社員と契約社員では、雇用期間や社会保険、キャリアパスなどに違いがあります。以下では、正社員と契約社員の違いについてまとめました。
比較項目 | 正社員 | 契約社員 |
雇用期間 | 期間の定めなし(無期雇用) | 期間の定めあり(有期雇用) |
契約更新 | 通常は不要、定年までの継続雇用が前提 | 契約ごとに更新の可能性あり |
社会保険 | 加入対象 | 条件を満たせば加入対象 (週20時間以上など) |
給与体系 | 月給制で、賞与・昇給制度が整備されていることが多い | 時給・日給制もあり、賞与や昇給がない場合もある |
勤務時間 | フルタイム勤務が基本 | フルタイムまたは短時間勤務 |
責任範囲 | 幅広い業務やマネジメントを任せやすい | 限定的な業務範囲で、昇進は想定されないことが多い |
キャリアパス | 昇進・昇格・異動など、あり | 原則、契約期間内での業務完遂が目的 |
無期転換ルール | 適用外 | 5年超の勤務で、無期雇用に転換可能 |
雇用期間
正社員は雇用期間に定めがない「無期雇用」で、基本的に定年までの長期雇用が前提です。一方、契約社員は、雇用期間に定めがある「有期雇用」となります。労働基準法では、有期労働契約の期間を原則3年と定めています。
また、契約社員として雇用する際は、企業側は「無期転換ルール」に注意しましょう。「無期転換ルール」とは、契約社員が同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、「無期雇用」に切り替えられる制度のことです。契約社員本人から申し出があれば、会社側は基本的にそれを断ることができません。
対象は、契約社員やアルバイトなど、有期契約で働いているすべての労働者です。無期転換後は、社員の役割や責任、就業規則などを整える必要があります。
参考:厚生労働省:労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール / 無期転換ルールについて
社会保険
原則、以下のような勤務条件を満たしていれば、契約社員も社会保険に加入する義務があります。
保険の種類 | 加入条件 |
健康保険・厚生年金 | 以下のすべてを満たす場合、契約社員でも加入義務あり。
(※2025年現在) |
雇用保険 | 以下の両方を満たす場合、加入義務あり。
|
労災保険 | すべての労働者が対象(労働時間・契約期間にかかわらず) |
参考:厚生労働省-社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について / 雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
行政指導のリスクを避けるためにも、条件を満たす従業員には正しく社会保険の加入手続きを行いましょう。
給与・賞与
給与体系も、正社員と契約社員で異なります。一般的に正社員は月給制で毎月一定額を受け取り、賞与(ボーナス)や昇給を制度化している企業が多いです。
一方の契約社員は、時給制や日給制など、会社ごとに異なります。賞与や昇給も、企業判断に任されるケースが一般的です。ただし、同一労働同一賃金の観点から、契約社員でも正社員と同様の業務・責任範囲を与え、待遇に差が生まれないようにすることも重要です。賞与を不支給とする場合、「正社員とは業務の責任範囲が異なるため」といった合理的な説明を用意しておきましょう。
勤務時間・責任範囲
勤務時間は、一般的に正社員も契約社員も同じ時間で働くことが多いです。しかし契約社員の場合、「週3勤務」や「短時間勤務」など、勤務形態に柔軟性を持たせている企業も存在します。責任範囲も、正社員の方が裁量や業務の幅が広く、部門マネジメントや業務改善提案など、より高いレベルの責任を伴うことが多いです。
契約社員は、部門横断的な業務やリーダーシップを求められる機会は少ない傾向にあります。たとえば、正社員が全体の進行管理を担い、契約社員がその中の一部の業務に専念するといった分担もよく見られます。
契約社員と派遣社員、パート・アルバイトとの違い
企業が人材を採用する際、契約社員・派遣社員・パート・アルバイトといった多様な雇用形態を選択できます。いずれも「非正規雇用」に分類されますが、雇用主・働き方・労働条件などが異なります。以下の表では、それぞれの違いをまとめました。
比較項目 | 契約社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト |
雇用主 | 勤務先企業 | 派遣元(派遣会社) | 勤務先企業 |
雇用期間 | 有期(1年・6ヶ月など)※更新あり | 有期(派遣契約に準ずる) | 定める場合が多い |
勤務時間 | フルタイムが中心 | フルタイムまたはシフト制 | 短時間勤務 |
社会保険の適用 | 条件を満たせば加入 | 条件を満たせば派遣元で加入 | 条件を満たせば加入 |
賞与・昇給 | 企業判断 | 原則なし(派遣元と契約内容次第) | 原則なし(勤務先企業の制度による) |
契約社員は、勤務先企業と直接雇用契約を結び、フルタイムで責任ある業務を任されるケースが多いです。正社員に近い働き方ですが、契約期間が決まっている点が大きな特徴です。
派遣社員は、雇用契約を結ぶ相手が「派遣元(派遣会社)」となり、実際の勤務先は別の「派遣先企業」となります。労務管理や給与の支払いは派遣元が行い、指揮命令は派遣先が出すという二重構造が特徴です。
パート・アルバイトは、短時間勤務で補助的な役割を担うことが多いです。学生や主婦、シニア層にニーズがある雇用形態となります。それぞれの特徴を理解したうえで、適切に使い分けていきましょう。
正社員・契約社員を雇用する企業側のメリット
企業にとって、正社員と契約社員はどちらも重要な戦力となります。以下では、正社員・契約社員を雇用する企業側のメリットについて解説していきます。
正社員のメリット | 契約社員のメリット |
|
|
【正社員】責任ある仕事を任せやすい
正社員は長期雇用が前提であるため、社員が責任感や主体性を持って働くようになるでしょう。 経営方針の理解や部門間の連携も深めやすく、判断を伴う業務やマネジメントポジションも任せやすいです。
また、社内教育やOJTを通じた中長期的な人材育成がしやすい点も、正社員の魅力です。会社の価値観や業務の進め方を踏まえ、より高度な業務にも段階的に任せられます。
【正社員】組織の安定・一体感をつくれる
正社員の場合、日常的に社内の意思決定や業務改善に関わるため、企業文化や経営理念、ビジョンへの理解が深まりやすい傾向があります。また、異動や昇進、ジョブローテーションなどを通じて複数の部署を経験すると、社内の人間関係や業務理解が広がります。結果、部門横断の連携や組織全体の一体感が強化されるでしょう。
さらに、正社員が長期的に定着すると、チーム内の信頼関係や心理的安全性が高まり、業務の効率化や職場の安定にもつながります。
【正社員】柔軟に業務指示ができる
多くの場合、正社員は職務や勤務地の範囲を広く設定しているため、業務内容の変更・異動・兼務といった柔軟な人事対応が可能です。
また、事業の再編や新規プロジェクトの立ち上げでも、社内の特性や事情を把握している正社員であればスムーズに業務を任せられます。事前の契約変更をすることなく依頼できるため、経営判断に基づく機動的な人材配置がしやすいです。さらに、部署を越えたキャリアパスや社内異動を展開すると、社内の人材を有効に活用しつつ、業務の属人化も防げるでしょう。
【契約社員】正社員登用前の試用期間になる
契約社員として一定期間雇用することで、正社員登用前の「見極め期間」として活用できます。企業・本人の双方にとっては、以下のようなメリットがあります。
企業側のメリット | 契約社員側のメリット |
|
|
このように「契約社員→正社員登用」を前提とした雇用は、育成コストを抑えながら、将来的なコア人材を育成できる手段となります。
【契約社員】一時的な人手不足が解消する
契約社員は、期間を限定して雇用できるため、繁忙期や新規プロジェクトなどで発生する一時的な人手不足を補いたい場合に有効です。たとえば、以下のようなケースで活用されています。
- 繁忙期(決算期・繁殖期など)の事務業務サポート
- 産休・育休社員の代替要員
- 一時的に増える顧客対応や短期プロジェクトへの対応
正社員を急いで採用・育成するよりも、必要なスキルを持つ人材を確保できる契約社員の方が、スピード感と柔軟性のある対応が可能です。コストや労務リスクを抑えながら、組織の継続性を保てる点は企業にとって大きなメリットでしょう。
【契約社員】採用コストを抑えられる
契約社員は、無期雇用の正社員と比べて、採用にかかるコストを抑えやすいです。契約期間を限定することで、契約満了に伴う自然な退職が可能なため、不要な人員の長期的な抱え込みを避けられます。結果的に、採用関連で余剰となるコストを減らせます。また、出勤日や勤務時間も正社員より柔軟に設計できるため、人件費全体のコスト管理もしやすいでしょう。
正社員・契約社員を雇用する企業側のデメリット
では反対に、正社員・契約社員を雇用する企業側のデメリットについて解説していきます。
正社員のデメリット | 契約社員のデメリット |
|
|
【正社員】固定的に人件費がかかる
正社員は、契約期間の定めがなく長期の雇用が前提となるため、人件費が固定的に発生します。毎月の給与や賞与、各種社会保険料、福利厚生費用などが継続的にかかるため、業績の変動や業務量の増減に柔軟に対応しづらい側面があります。
特に、急な業務縮小や組織再編を行う際には、解雇や配置転換が難しく、人件費の調整に制約が生じることも少なくありません。そのため、経営計画に沿った慎重な人員計画やコスト管理が必要です。
【正社員】採用ミスマッチのリスクが大きい
正社員は長期雇用を前提とするため、採用時のミスマッチが企業に与える影響が大きくなります。たとえば以下のような形でミスマッチが生じるのは、企業にとってマイナスです。
- スキルや経験が期待に達していない
- 社風やチームとの相性が合わない
- 教育・配置転換・動機づけなどに追加コストがかかっている
- 業務効率やチームの生産性が下がっている
こうしたリスクを減らすには、業務内容の明確な提示や職場体験・インターン導入といった入念な採用プロセスの設計が重要になります。
【正社員】簡単に解雇できない
正社員雇用は法律上、企業側の都合で一方的に解雇できません。労働契約法第十六条では、「客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない限り解雇は無効」としています。そのため「勤務態度に問題がある」「配置転換や改善指導後も状況が変わらない」というケースでも、指導や教育を通して改善していく必要があります。
対策として、採用段階で適性をじっくり見極めるために、試用期間を設定しましょう。「契約社員から正社員登用」「業務委託から正社員登用」といった段階的な採用フローが効果的です。
【契約社員】社員の組織への帰属意識が低下しやすい
契約社員は有期雇用であるため、正社員と比べて企業に対する帰属意識やエンゲージメントが低くなりやすい傾向があります。契約期間の終了が前提である以上、「一時的な職場」と捉える人も少なくありません。たとえば、以下のような姿勢・感情になりやすいです。
- 組織のビジョンや中長期目標への関与が薄くなる
- 改善提案や業務改革などに主体的に関わりにくい
- チームに参加しにくいと感じやすい
- 昇進や異動が見込めないと感じ、意欲が低下する
これを防ぐには、「契約社員も含めた情報共有や意見交換の機会を増やす」「正社員登用制度の明示」など、モチベーションを向上させる取り組みが欠かせません。
また、評価制度や表彰制度の対象に契約社員も含めることで、日々の成果や貢献が正当に評価される仕組みを整えることも効果的です。キャリアパスの見える化や、定期的なフィードバックの機会を設けて、職場の一体感を高めていきましょう。
【契約社員】長期的な人材育成がしにくい
契約社員は有期雇用であるため、一定期間で契約が終了する前提の働き方です。企業は、長期的なキャリア形成の提案や、計画的な人材育成が難しいと感じるかもしれません。
「業務ノウハウの継承が不安定」「育成コストに見合うリターンが得にくい」という点は、契約社員の短所となります。
【契約社員】待遇・給与設計の見直しが必要
契約社員を雇用する際は、同一労働同一賃金の原則により、正社員と不合理な格差がないかを見直す必要があります。特に、職務内容や責任が類似している場合は注意が必要です。具体的な見直しのポイントとしては、以下のような項目が挙げられます。
- 基本給や賞与、退職金などの支給有無
- 福利厚生(通勤手当、住宅手当、健康診断など)
- 昇給・昇格の有無とその基準
待遇の違いが不透明であると、労使トラブルや行政指導のリスクにもつながります。制度面の整備と従業員への丁寧な説明に時間を要する点は、契約社員のデメリットといえるでしょう。
契約社員から正社員登用する7つのステップ
契約社員として一定期間働いてもらった後に正社員として採用する方法は、早期離職やミスマッチのリスクを減らします。 ここでは、契約社員から正社員へスムーズに切り替える7つのステップをご紹介します。
1.正社員登用制度を整備する
契約社員を正社員登用する際には、事前に社内で登用制度の内容を整備しておきましょう。たとえば以下のように項目を分類し、評価基準や条件を策定します。
項目 | 内容の例 |
登用対象者の条件 | 勤続〜年以上、勤務態度・評価基準を満たす者 など |
評価基準 | 勤務成績、スキル、協調性、勤務態度 など |
登用フロー | 評価 → 上司推薦 → 面談 → 人事部門による最終判断 |
選考方法 | 書類選考、面接、課題提出 など |
社内周知の方法 | 社内専用のポータルサイトで報告、就業規則への明記など |
正社員登用制度を用意しておくと、契約社員に将来のキャリアパスを提示できます。正社員登用のチャンスがあることで、働く意欲が向上するでしょう。また、人材育成方針の明確化によって、組織の中長期的な人材戦略を描きやすくなります。「自分を評価してくれている会社」と感じてもらえるよう、登用の基準やプロセスを明文化しておきましょう。
2.対象者を選定する
正社員登用制度を整備したら、次に候補者を選定しましょう。対象者を選ぶ際には、以下のポイントに注目しましょう。
- 「今の実力」と「将来の成長性」に注目する
- 自社のコア業務を担える人材かどうかを見極める
- 部署やチームのバランスも踏まえて判断する
企業の事業戦略と照らし合わせながら、対象者を選んでいきましょう。
3.正社員登用の意思を本人に確認する
候補者を選定したら、本人の意思を確認していきましょう。たとえば、次のような質問が有効です。
項目 | 質問例 |
登用意欲の有無 |
|
キャリア志向 |
|
ライフスタイルとの適合 |
|
勤務条件への理解 |
|
ヒアリングする際は一方的な通告ではなく、対話を意識することが重要です。また、希望だけでなく、不安や懸念点も聞き出しておきましょう。
本人の意思を丁寧に確認しておくことで、企業と社員、双方が納得したうえで登用を進められ、離職リスクを回避できます。キャリア面談や評価面談の場を活用して、価値観や働き方の希望をヒアリングしておきましょう。
4.正社員登用の選考を実施する
本人の意思確認が取れたら、事前に定めた基準に基づいて、正社員登用の選考を行いましょう。公正で透明性の高い選考フローが、候補者との信頼構築につながります。
面接する際は、業務理解度・姿勢・適性を確認していきます。「今後のキャリアビジョン」といったテーマに、小論文・レポートを提出してもらう方法も有効です。選考に関わるすべての関係者が、共通認識を持って評価を進めていきましょう。
5.正社員としての雇用契約を結ぶ
正社員登用の選考を通過したら、契約社員から正社員への切り替え手続きを正式に進めます。雇用条件が変更となるため、企業側は以下の書類を取り交わしましょう。
書類名 | 内容 |
雇用契約書 | 雇用形態・職務内容・給与などを記載 |
労働条件通知書 | 賃金・労働時間などの条件明記 |
誓約書・身元保証書 | 法令遵守・秘密保持などの誓約 |
雇用内容があいまいだと、後にトラブルにつながる恐れがあります。労働条件の変更点は口頭だけでなく、文書でしっかり説明・記録することが重要です。また、登用時には社員本人にも条件説明の場を設け、納得感のある形で新たなスタートを切ってもらいましょう。
6.就業規則・社会保険などの変更処理を進める
正社員登用に伴い、就業規則・社会保険などの変更処理を進めていきましょう。登用前の勤務形態がフルタイム勤務に近ければ、契約社員も 健康保険・厚生年金・雇用保険 の加入対象となり、正社員登用後も社会保険は引き続き適用されます。
ただし、正社員登用によって給与体系が変わり、賃金に大きな変動があった場合は変更の手続きをする必要があります。特に、基本給や手当などの固定的な賃金に変更があり、3か月間の平均報酬月額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差が出たときには、「被保険者報酬月額変更届」を提出します。
手続きが遅れると保険料の過不足が生じる恐れがあるため、給与改定後は速やかに確認・対応することが重要です。人事・労務担当者は登用スケジュールと連動させて、社会保険の変更処理も抜け漏れなく進めましょう。
参考:日本年金機構
7.正社員登用後のサポート体制を構築する
契約社員から正社員に登用した直後は、環境の変化に戸惑いや不安を感じやすいため、定着と戦力化を支援する体制づくりが不可欠です。以下のようにサポートを丁寧に行うと早期離職の防止になるだけでなく、社員のモチベーション維持につながります。
サポート内容 | 具体的な取り組み例 |
OJT(現場教育) | 上司・先輩社員による実務指導し、段階的に業務を割り当てる |
メンター制度 | 年次の近い先輩社員を専任メンターに任命 |
1on1面談の定期実施 | 月1回、上司と進捗や悩みを共有し、フィードバックの機会を設ける |
キャリアパスの提示 | 昇格・異動の可能性を明示し、将来像を描けるよう支援する |
研修制度の整備 | ビジネススキルや専門知識を得るための研修を実施する |
フォロー施策は少なくとも6か月〜1年間継続するのが理想です。一律的な対応ではなく、職種・個人の特性に合わせて調整していきましょう。
「業務委託から正社員登用」という新たな採用手段
正社員登用のパターンとして、これまで「契約社員(もしくはアルバイト)から正社員登用」というステップが一般的でした。しかし、最近では「まずは業務委託でスキルや相性を見極め、その後に正社員として登用する」という採用スタイルも広がっています。
「業務委託から正社員登用」では、人材との相性を見極めつつ、採用コストを最小限にできます。特に、以下のようなニーズを持つ企業に適しているでしょう。
- いきなり正社員採用するのはリスクが高い
- 特定スキルを持つプロフェッショナルを見極めたい
- 業務委託で成果を確認した上で正社員として迎えたい
「業務委託から正社員登用」という方法は、採用の選択肢を広げたい企業にとって有力な手段となるでしょう。
▼関連記事:【企業向け】業務委託と正社員をどう切り替える?メリットや手続きの流れなど徹底解説
業務委託から正社員登用する企業側のメリット3つ
この章では、「業務委託から正社員登用」のメリットについて解説します。
1.スモールスタートで人材との相性を見極められる
業務委託は雇用契約を伴わず、業務単位・期間限定での依頼が可能なため、スモールスタートで人材との相性を見極められます。契約社員とは異なり、はじめから長期前提の雇用関係を結ぶ必要がないため、低リスクでトライアル的な業務依頼が可能です。たとえば、以下のような点を実務ベースで相性を自然に確認できます。
- スキルや実務遂行能力
- チームとのコミュニケーション力
- 自社カルチャー・業務スタイルとの適合度
- 指示理解力や課題への主体的な取り組み姿勢
さらに、契約社員と異なり雇用関係ではないため、ミスマッチがあっても社会保険の手続きや雇用契約の終了といった煩雑な対応が不要です。「まずは業務委託から」であれば、正社員登用に進む前に十分な見極め期間を持てるため、採用の質と定着率を高められます。
2.即戦力人材を確保できる
業務委託として一定期間実務を任せると、業務内容や企業文化を理解した状態で正社員登用が可能です。また多くのフリーランスは、自ら業務を組み立てられる「自走力」があり、スピード感をもって仕事を進めます。そのため企業は、教育コストや立ち上がり期間を抑えつつ、早期での成果創出が期待できます。特に以下のような状況において効果的です。
- 専門職やプロジェクトベースの即戦力が必要
- 少人数チームで柔軟に人材を活用したい
- 採用ミスマッチを避けたい
業務委託であれば、成果を確認したうえで正社員化できるため、選考コストやリスクを最小限に抑えられます。
3.転職市場にいない優秀層と出会える
契約社員採用の場合、募集範囲や応募者層が限られることが多いです。一方で、業務委託は案件単位での依頼が基本のため、フリーランスや副業人材など、多様な働き方を選ぶ専門スキル保持者と出会えます。たとえば、以下のような人材とのマッチングが期待できます。
- 専門スキルを活かして副業や業務委託で新しいチャレンジをしている人
- 転職市場には出ていないが、実務経験豊富で即戦力となる人材
- フリーランスとして高い評価を受けているが、安定的な正社員ポジションも視野に入れている人
特に専門職や技術職、クリエイティブ職など、即戦力人材が重要視される領域で効果的な採用手法といえるでしょう。業務委託から正社員登用を目指す場合、通常の転職市場や求人広告に出てこない優秀な人材と出会うチャンスが広がります。
▼関連記事:業務委託と正社員、どっちがいい?両者のメリットや正社員登用のステップまで解説
即戦力人材を採用したい企業は、「Workship CAREER」がおすすめ!
ここまで、正社員・契約社員の違いやメリット・デメリットなど、ご紹介してきました。特に最近では、「契約社員→正社員」よりも「業務委託→正社員」の採用アプローチが注目を集めています。
「業務委託から正社員登用をしてみたいけれど、どうすればいいかわからない」という企業には、『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』がおすすめです。
Workship CAREER
では、「業務委託契約からの正社員転換」のサポートだけでなく、人事課題までトータルに支援いたします。
Workship CAREERの特長
- トランジション採用の導入:業務委託契約からスタートし、その後正社員登用への切り替えを支援いたします。
- 豊富な人材データベース:エンジニア、デザイナー、PMなど、約5万人以上のフリーランスネットワークから、企業のニーズに合った候補者をご紹介いたします。
- 人事のプロが採用から育成まで一貫して伴走:労務管理や育成制度設計など、貴社の人事課題をトータルに解決いたします。
「教育コストをかけずに、経験者をチームに迎えたい」「採用のミスマッチを防ぎたい」とお考えの企業は、一度Workship CAREERにご相談ください。無料相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。
▼Workship CAREER:サービス資料のダウンロードはこちら

- Workship CAREERのサービス内容
- ご契約の流れ
- 取引実績
- 関連サービス

リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェント「Workship CAREER」の編集部です。採用に役立つ情報を発信していきます。