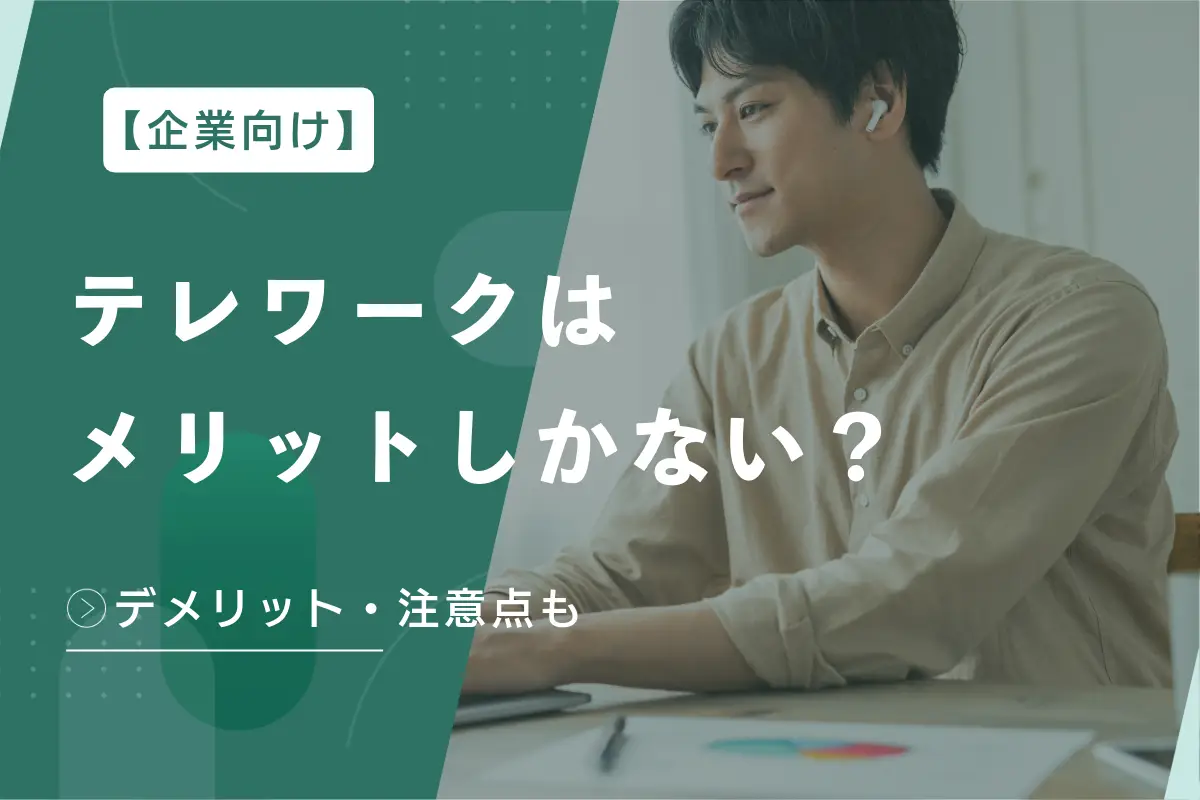近年、「業務委託」を活用する企業が増加。特に、即戦力の確保やコスト調整の観点から、多くの中小企業やスタートアップ企業が業務委託を積極的に活用しています。
しかし、「思ったように成果が出ない」「ノウハウが社内に残らない」といった悩みを抱える声も少なくありません。情報漏えいや契約上での問題など、トラブルを未然に防ぐには、正当な取引と良好な信頼関係が欠かせません。
そこで本記事では、企業側の業務委託のメリット・デメリットやリスク対策、よくある業務委託のトラブル事例など、解説します。「業務委託での課題を解決したい」「今後、業務委託を導入して自社の成長につなげたい」と考える企業は、ぜひ最後までご覧ください。
業務委託契約とは?
業務委託契約とは、企業が外部の個人や法人に対し、業務の遂行を依頼する契約形態のことです。業務委託契約には大きく分けて以下の3種類があり、それぞれ目的や責任範囲が異なります。
種類 | 内容の特徴 | 主な業務委託の例 |
請負契約 |
| Webサイト制作、アプリ開発など |
委任契約 |
| 税務申告、登記手続きなど |
準委任契約 |
| システム運用、事務代行など |
たとえば、完成した成果物を納品する案件では「請負契約」、法律行為を委託する際は「委任契約」、継続的に支援や作業を依頼したい場合は「準委任契約」となります。
業務委託は、「スピーディーに業務を依頼できる」「予算に合わせて契約できる」といった、即時性と柔軟性が大きな魅力です。特に事業が成長段階にある時期や、売上の先行きが読めない時期に最適でしょう。以下では、業務委託のメリットについてさらに深堀りしていきます。
業務委託で得られる企業側のメリット5つ
ここでは、業務委託で得られる企業側のメリットを5つ紹介します。
業務委託で得られる企業側のメリット5つ |
|
1.専門性の高い人材にすぐ仕事を依頼できる
業務委託では、特定のスキルや知見を持つプロフェッショナルに、必要なタイミングで迅速に業務を依頼できます。たとえば、特定スキルを持つ人材を正社員採用したい場合、なかなか候補者が見つからず、時間を要することもあるでしょう。
業務委託であれば、必要なときに必要な分だけ、外部に仕事を委託できます。数週間〜数カ月といった短期間での依頼や、プロジェクト単位での契約も可能です。特に、リソース不足を一時的にカバーしたいときや、業務の変動量が多いときに活躍します。
2.業務効率と開発スピードが向上する
業務委託では、多くのケースで即戦力人材が仕事を進めるため、社内の作業効率と開発スピードが向上します。経験豊富な人材によるタスク遂行により、社内だけの対応よりも、すばやい成果創出が期待できます。
たとえば外部のエンジニアに新機能の開発を委託し、リリースまでの期間が半分に短縮した、という実例もあります。組織全体の生産性が高まる点は、業務委託の導入で得られる最大のメリットといえるでしょう。
3.新しいノウハウや視点を社内に取り込める
最新のノウハウや、多様な視点を社内に取り入れられる点も、業務委託の魅力です。特に、急速に変化するIT・Web業界やテクノロジー分野では、外部人材の知見が社内に気づきをもたらすでしょう。
社外の視点が、業務改善やイノベーションのきっかけになることも少なくありません。企業にない新しい視点は、組織の競争力を高めるトリガーとなるでしょう。
4.事業フェーズに合わせてコストを調整できる
業務委託は、正社員のように給与(固定費)が発生しません。特定の期間や業務量に応じて契約する、外注費に該当します。事業の成長フェーズや、繁忙期・閑散期に合わせて依頼業務を調整できるため、柔軟なコスト調整が可能です。
そのため新サービスの立ち上げ時だけ外部のマーケターに協力してもらい、広告運用やプロモーションの仕組みを整えた後に契約を終了する、といった対応もできます。人件費の変動費化によって経営判断の自由度が高まる点は、スタートアップ企業や中小企業にとって嬉しいメリットとなるでしょう。
5.バックオフィス業務の委託でコア業務に集中できる
バックオフィス業務を外部に委託すると、社員はコア業務に集中できます。経理、労務、総務といった日常的かつ専門性の高い業務は、意外にも社内リソースを圧迫しがちです。ノンコア業務を外部の専門家に任せると、業務効率の促進と社員の負担軽減が期待できます。
たとえば、月次の経理処理や給与計算をアウトソースすると、社内メンバーは営業活動や企画立案など、売上や事業成長に直結する業務に注力できます。また、専門のITシステムに慣れている人材に業務を依頼すると、システムの活用法や使い方を共有してもらえるでしょう。企業のDX化を進めるきっかけにもなり、スムーズなデジタル化への移行が期待できます。
参考:採用代行はフリーランスに業務委託できる?メリットや注意点、おすすめサービスを紹介 | ピタリク
業務委託はやめたほうがいい?企業側のデメリット7つ
では反対に、業務委託のデメリットについて解説していきます。
業務委託のデメリット7つ |
|
1.社内にノウハウが蓄積しない
業務委託では専門的な作業を外部人材に任せるため、工夫をしなければ知識やスキルが社内に蓄積されにくいというデメリットがあります。たとえば、Web開発や広告運用を委託した場合、成果の出し方や改善方法といったプロセス・ノウハウが社内に残らないケースが存在します。
仮に同じような問題が発生したとき、社内メンバーだけでは対処できず、再び外部に頼らざるを得ない、という事態になりかねません。コスト面でも負担が継続し、社内の自走力を育てにくくなるという点は注意が必要です。
2.成果物や業務の品質にバラつきがある
業務委託では、担当者のスキルや仕事の進め方が一律ではないため、成果物や業務の品質にバラつきが出やすいです。たとえば、同じ業務を複数の委託先に依頼する場合、納品物の完成度や対応の丁寧さに差が出ることがあります。結果的に社内での修正や手戻りが発生し、かえって負担が増加するかもしれません。
品質管理の基準を明確にしておかなければ、「イメージと違う」「仕様とずれている」といったトラブルに発展しやすいため、注意が必要です。
3.情報漏えいのリスクがある
業務委託では、外部人材に機密情報や顧客データを共有する場面もあるでしょう。情報管理の取り扱いや、使用ルールを整備しておかなければ、情報漏えいのリスクがつきまといます。たとえば、Webサービスの開発を委託する際に、「アクセス権を付与したシステム情報が流出した」「社外の作業環境から顧客データが漏れた」といったことも起こり得ます。
特に委託先がフリーランス(個人事業主)や、小規模な事業者の場合、セキュリティ体制が万全でないこともあるでしょう。また意図的でなくても、操作ミスや管理の甘さから、問題が発生する可能性もあります。
4.コストが高くなることがある
業務委託では、割高になるケースも存在します。たとえば、短期間で高い専門性が必要な業務や、修正回数が多い案件では、想定以上に費用がかかることがあります。また、契約外の追加作業に都度費用が発生する場合、コスト管理が難しいと感じるかもしれません。
さらに成果物の品質が低いために、やり直し・再委託が続くと、二重の支出が発生して費用が増大する可能性があります。
5.意思疎通や一体感の醸成が難しい
業務委託は外部企業や外部人材との契約であるため、チームの一体感を醸成しにくいです。特にリモートの場合、雑談や確認の機会が減るため、意思疎通や認識にズレが起こりやすいでしょう。
たとえば、業務変更を伝えなかったために、委託先が「旧仕様で作業を進めてしまう」といったミスが生じることもあります。こういった行き違いが続くと信頼関係に支障をきたし、業務に滞りが発生する場合もあります。
6.進捗管理が必要となる
業務委託では、常時目の届く範囲で仕事をしているわけではないため、進捗状況が把握しにくいと感じることもあるでしょう。スケジュールの遅延に気づいたときには、「すでに手遅れ」というケースも珍しくありません。
たとえば、Webサイト制作を丸ごと委託した際に、設計段階でのズレに気づかず、納品直前で大幅な修正が必要になった、といった事態も起こり得ます。特にタスクのボリュームが大きい場合や、依頼内容が抽象的な場合、進行状況がブラックボックス化しやすいため注意が必要です。
7.契約後にトラブルが発生する場合がある
業務委託は「契約ありき」の関係になるため、契約内容の不備や認識のズレが原因でトラブルに発展するケースがあります。たとえば、「修正対応の回数」「納品後の不具合の対応」などが不明瞭だと、納品物に対する不満や追加費用の請求で揉めることもあります。
また稀に、委託先による業務の途中放棄や、納品日の遅延といったケースも存在します。こうしたトラブルの発生は、スケジュール全体が狂うだけでなく、顧客対応に支障が出るため対応策を練ることが不可欠です。
▼関連記事:【企業向け】業務委託と正社員をどう切り替える?メリットや手続きの流れなど徹底解説
業務委託で企業側がとるべきリスク対策8つ
ここでは企業側がとるべき、業務委託でのリスク対策を8つ紹介します。
業務委託における8つのリスク対策 |
|
1.知識やノウハウが社内に蓄積するよう工夫する
業務委託では、「知識やノウハウが社内に残りにくい」という課題があります。こういったリスクを防ぐには、外部人材に業務フローや設計背景をドキュメント化してもらい、社内で共有できるよう仕組み化することが重要です。
また、定期的なノウハウ共有の場を設け、社内担当者をアサインさせて共同でタスクを進める方法も効果的です。外部に「丸投げ」ではなく、将来的に自社で内製化できるよう進めていきましょう。
2.品質基準や納期など明示する
業務委託では、求める成果物の基準の設定が欠かせません。特に品質に対する感覚は人によって異なるため、言葉だけのやり取りでは不十分です。
納品後に「思っていたものと違う」とならないためにも、成果物の仕様や品質基準、納期などを、あらかじめ文書で明確にしておきましょう。できるだけ具体的な内容を契約書に記載しておくと、発注者と受注者、双方の認識の違いを防げます。
また、途中経過を確認する中間レビューや、マイルストーンの設定も効果的です。要件を可視化し、進捗を確認しながら進めると、安定した品質と納期遵守が実現しやすくなります。
3.業務フローの手引きを作成する
業務委託では、社内のルールや進め方が伝わっていないと誤った手順で作業が進み、ミスや手戻りの原因になります。
そのため、業務の流れや使用ツール、関係者の役割分担などをまとめた、「業務フローの手引き」を用意しておくといいでしょう。これにより、外部の委託先がスムーズに業務に参加できるだけでなく、誰が見ても業務の全体像が把握できる状態を構築できます。
さらに、手引きは業務の属人化を防ぎ、今後の委託や内製化にも活用できます。業務を標準化し、誰もが同じ品質で対応できる環境作りが委託の成功につながるでしょう。
4.セキュリティ対策を徹底する
業務委託では、外部人材に業務システムや顧客データなどの重要情報へアクセスしてもらう場面もあるでしょう。情報漏えいのリスクを防ぐには、以下のような、具体的なセキュリティ対策が欠かせません。
- アクセス権限を最小限に設定する
- 機密保持契約(NDA)を結ぶ
- 業務用アカウントの発行やログ管理を行う
また、使用するツールの選定も重要です。SlackやGoogle Workspaceなどを使う際の決まりや社内ルールを整備し、安全に運用できる体制を整えておきましょう。万が一のトラブルに備え、定期的な見直しや教育も実施し、リスクを最小化するのもポイントです。
5.委託業務の内容を明確にする
業務委託契約で委託範囲があいまいだと、「追加作業でトラブルになる」「納品の基準が違う」といった問題が起こりがちです。特に、抽象的な表現や口頭だけのやり取りでは、認識の相違が発生しやすいでしょう。
こうしたリスクを防ぐには、「委託業務の範囲や目的」「成果物の基準」「納期」といった情報の明文化が不可欠です。契約書だけでなくタスク一覧も用意し、担当範囲を明確にしておくと安心です。
6.進捗管理の体制を整える
業務委託では、進捗状況が見えにくく、納期直前に問題が発覚するケースもあります。そのため、進捗管理のルールやチェック体制の整備が欠かせません。たとえば、定例ミーティングの実施や、チャットツール・プロジェクト管理ツールの活用といった工夫が必要です。タスクを可視化すると、進行状況の把握がしやすくなります。
また、進捗の遅れが発生した際の報告ルールや、途中のレビュー・フィードバックの方法も決めておきます。企業側が一定のマネジメント体制を持つことで、業務委託でよりスムーズに成果を出せるようになるでしょう。
7.業務委託に関する社内教育を実施する
外部人材との仕事を円滑に進めるには、社員全員が業務委託の基本的な知識や注意点を理解しておく必要があります。そのため関係部門や担当者に対し、業務委託のルールや進め方を共有する社内研修やマニュアルの整備が欠かせません。契約書のフォーマットや管理ツールなども共有しておくと、社内での判断や対応がスムーズです。
必要に応じて法務・経理といった部門とも連携し、横断的に業務委託を管理・運用できる体制をつくりましょう。社内教育は法的リスクの防止となるだけでなく、委託効果を最大化する上でも重要です。
8.信頼できるフリーランスエージェントやサービスを活用する
業務委託では、スキルや信頼性の高い人材の見極めが成功を左右します。特に、個人との直接契約は、スキルのばらつきや、契約上のトラブルに発展することもあるでしょう。そのため、実績やサポート体制の整ったフリーランスエージェントや、業務委託マッチングサービスの活用がおすすめです。
たとえば「Workship」では、スキル評価や契約支援といった機能・サポートが充実しているため、企業側は安心して業務を委託できます。信頼できるサービスの活用によって、契約上のリスクを回避しつつ、効率よく自社が求める人材を探し出せます。
▼Workshipについてさらに詳しく知りたい方は、以下からサービス資料をダウンロードしてください。

業務委託でよくあるトラブル事例
業務委託は柔軟な人材活用ができる一方で、進め方を誤るとさまざまなトラブルに発展します。ここでは、実際によくある業務委託のトラブル事例を紹介し、未然に問題を防止する方法を解説します。
業務委託でよくあるトラブル事例 |
|
業務の実態が偽装請負になっている
業務委託契約にもかかわらず、実際の働き方が「労働者」に近い場合、偽装請負とみなされる可能性があります。たとえば「毎日オフィスに出社して朝会に必ず参加してください」と命じると、実態として雇用関係に近くなり問題視されやすいです。偽装請負に該当する業務の依頼は、法律に違反する行為となり、是正指導や損害賠償の対象になることもあるため注意が必要です。
偽装請負を防ぐには、「成果物の基準」や「作業の到達目標」を契約前に共有することが重要です。勤務時間・やり方は指示をせず、「何を・どこまでやるのか」という内容を書面等に記載して交付します。また、報告のタイミングや、連絡がとりやすい時間帯は事前に知らせてもらい、外部人材の稼働状況が把握できるようにしておきましょう。
▼参考:厚生労働省-偽装請負について
知的財産権の帰属があいまい
成果物の知的財産権(著作権や特許権など)が、「誰に帰属するのか」が曖昧だと、後々トラブルになります。たとえば、外部に依頼したシステム開発やデザインの権利が、「発注企業にあるのか・委託先に残るのか」といった点が不明確だと、二次利用や改変に問題が生じます。
対策として、業務委託契約書や秘密保持契約書といった書類に、知的財産権の帰属を明確に記載しましょう。使用許諾の範囲を具体的に定めておくと、将来的な権利関係のトラブルを避けられます。
報酬の支払い時期や条件が不明確
業務委託契約において、報酬の支払い時期や条件がはっきりしていないと、発注者と受注者の間で問題が発生しやすいです。たとえば、「納品」の定義が曖昧で支払いが遅れるケースや、進捗に応じた分割払いの条件が不明確でトラブルになることがあります。
こうした問題を避けるには、支払いのタイミングや金額、条件を、契約書に具体的に明記することが欠かせません。報酬の条件を、発注者と受注者の双方が理解・合意した上で契約することが重要です。
業務委託契約書を交わしていない
口頭やメールだけで業務委託を進めるケースでは、契約内容が曖昧で、トラブルが起こりやすくなります。たとえば、業務範囲や納期などが不明確であることから、誤解や争いが生じやすいです。
対策として、必ず書面または電子的記録で契約書を作成し、発注者と受注者の双方で内容を確認・合意した上で契約します。業務委託契約書を作成しておくと、責任範囲や業務内容が明確になり、万が一のトラブル時にも迅速に対応できます。
また契約内容を記載した書面の交付・記録は、2024年に施行されたフリーランス新法でも義務化されています。法的な罰則を受けないためにも、業務委託契約書は必ず交付しておきましょう。
募集内容と実際の業務に乖離がある
業務委託の募集内容と実際の依頼業務が異なる場合、受託者が「期待していた業務と違う」と感じ、業務遂行に支障をきたすこともあります。たとえば、募集時には「単純な作業」と説明していたのに、実際は「高度な専門知識や長時間の対応」が必要だったケースが該当します。
そのため業務委託の募集では、業務内容を具体的かつ詳細に伝えましょう。特にSNSや自社ブログでの募集は、記載方法やフォーマットが自由であるため、情報を端的に伝えがちです。あいまいな募集は候補者が戸惑うだけでなく、マッチングの質も低下します。さらに、虚偽または誤解を生じさせる募集の表示は違法です。募集情報は、常に正確かつ最新の内容にしておきましょう。
▼関連記事:【企業向け】フリーランスと正社員の違いとは?両者のメリットや注意点など徹底解説
正社員と業務委託の違い
人材獲得にはさまざまな方法がありますが、「正社員」と「業務委託」は大きく性質が異なります。正社員は企業と雇用契約を結び、会社の指揮命令のもとで働きます。一方、業務委託は、成果物の提供や作業の実施で報酬を支払う契約です。発注者は受注者に対し、労働時間や作業場所への指揮命令ができません。
以下の表では、両者の違いについてまとめました。
項目 | 正社員 | 業務委託 |
契約形態 | 雇用契約 | 業務委託契約(請負・委任・準委任) |
適用対象の法律 | 労働基準法など | フリーランス新法など |
報酬形態 | 月給・年俸制など | 成果物・業務単位での報酬 |
社会保険・福利厚生 | 企業が負担・提供 | 自己負担 |
指揮命令関係 | あり(企業が業務指示を行う) | なし(業務の進め方は委託先に一任) |
勤務時間・勤務場所 | 原則、会社が指定 | 原則、自由 |
雇用期間 | 長期(無期雇用) | 短期・中期が多い(契約期間に応じる) |
適切に使い分け、事業の成長を効率的に支援する体制を整えていきましょう。
正社員と業務委託、どっちがいい?目的別で使い分けよう
「正社員採用と業務委託、どちらが自社に合っているかがわからない」という企業に向けて、ここでは正社員採用と業務委託が適しているケースについてまとめました。
「正社員」が適しているケース | 「業務委託」が適しているケース |
|
|
上記のように、長期的に人材を採用して業務を幅広く任せたいときは「正社員」、一時的な業務だけを任せたいときは「業務委託」と使い分けると、人材活用の効率化が向上するでしょう。自社の目的や事業状況など、多角的な視点で判断することがポイントになります。
業務委託から正社員登用という新たな採用手法の3つの魅力
近年、注目を集めているのが「業務委託からの正社員登用」という採用手法です。業務委託で実務を経験してもらった後、企業は候補者の働きぶりやスキルを確認した上で、正社員化を打診できます。実績に基づいた判断となるため、採用ミスマッチを最小限にできる点が大きなメリットです。
ここでは、そんな「業務委託から正社員登用」の3つの魅力について詳しく解説します。
業務委託から正社員登用する3つの魅力 |
|
1.自社業務や組織体制に詳しい人材を採用できる
「業務委託からの正社員登用」のメリットは、候補者に業務委託で一定期間働いてもらった後、自社の業務や企業文化を深く理解した上で正社員採用につなげられる点です。たとえば新規プロジェクトに参加していた外部人材が、正社員登用後も即戦力として活躍した、というケースがあります。
最初から関係性が構築された上での採用は、企業側・人材側の双方ギャップが生じにくいため、納得度の高い採用となります。
2.正社員採用に伴うコストを削減できる
「業務委託からの正社員登用」では、通常の採用活動で必要なコストが不要である点が魅力です。具体的には、「求人広告の掲載料」「人材紹介会社への手数料」などがカットされます。
さらに、すでに自社業務を経験している人材の採用は、ミスマッチのリスクが低いため、定着率の向上が見込める点もメリット。結果、長期的に戦力となる人材の確保が期待できます。
3.プロジェクトへの早期アサインが期待できる
外部人材を正社員化すれば、採用後すぐにプロジェクトへアサインしてもらえるでしょう。社内のルールやチーム体制を理解しているため、通常の新入社員と比べて、オンボーディングや研修にかかる時間を大幅に短縮できます。
特に、スピード感が求められる現場や、即戦力を早期に確保したい現場では、大きなアドバンテージとなるでしょう。
▼関連記事:業務委託と正社員、どっちがいい?両者のメリットや正社員転換のステップまで解説
業務委託から正社員登用を視野に入れるなら、『Workship CAREER』がおすすめ!
業務委託は、即戦力人材を柔軟に活用できる反面、「ノウハウの社内蓄積が困難」「品質基準のバラつき」といった課題もあります。「社内共有の仕組み化」や「詳細に条件を記載した業務委託契約書の交付」など進め、リスク対策を講じておきましょう。
業務委託は、うまく活用すると事業成長を支える有益な人材獲得の手段となります。特に、「業務委託から正社員登用」は自社業務に精通した人材の採用となるため、意思決定の満足度が高く離職リスクを抑えられます。
『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』では、業務委託から正社員登用を図りたい企業をサポートいたします。豊富なIT・DX人材のネットワークから、自社にマッチした候補者をスピーディーにご紹介いたします。
Workship CAREERの特長
- トランジション採用の導入:業務委託契約からスタートし、その後正社員登用への切り替えを支援いたします。
- 豊富な人材データベース:エンジニア、デザイナー、PMなど、約5万人以上のフリーランスネットワークから、企業のニーズに合った候補者をご紹介いたします。
- 人事のプロが採用から育成まで一貫して伴走:定例会議やスポット対応など、貴社の人事課題をトータルに解決いたします。
「まずは業務委託で相性を確かめたい」「長期的な活躍を見据えた採用をしたい」とお考えの方は、Workship CAREERをご検討ください。
Workship CAREERでは、貴社の採用課題や募集内容をヒアリングした上で、最適な人材をご紹介いたします。無料相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。
- Workship CAREERのサービス内容
- ご契約の流れ
- 取引実績
- 関連サービス

リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェント「Workship CAREER」の編集部です。採用に役立つ情報を発信していきます。