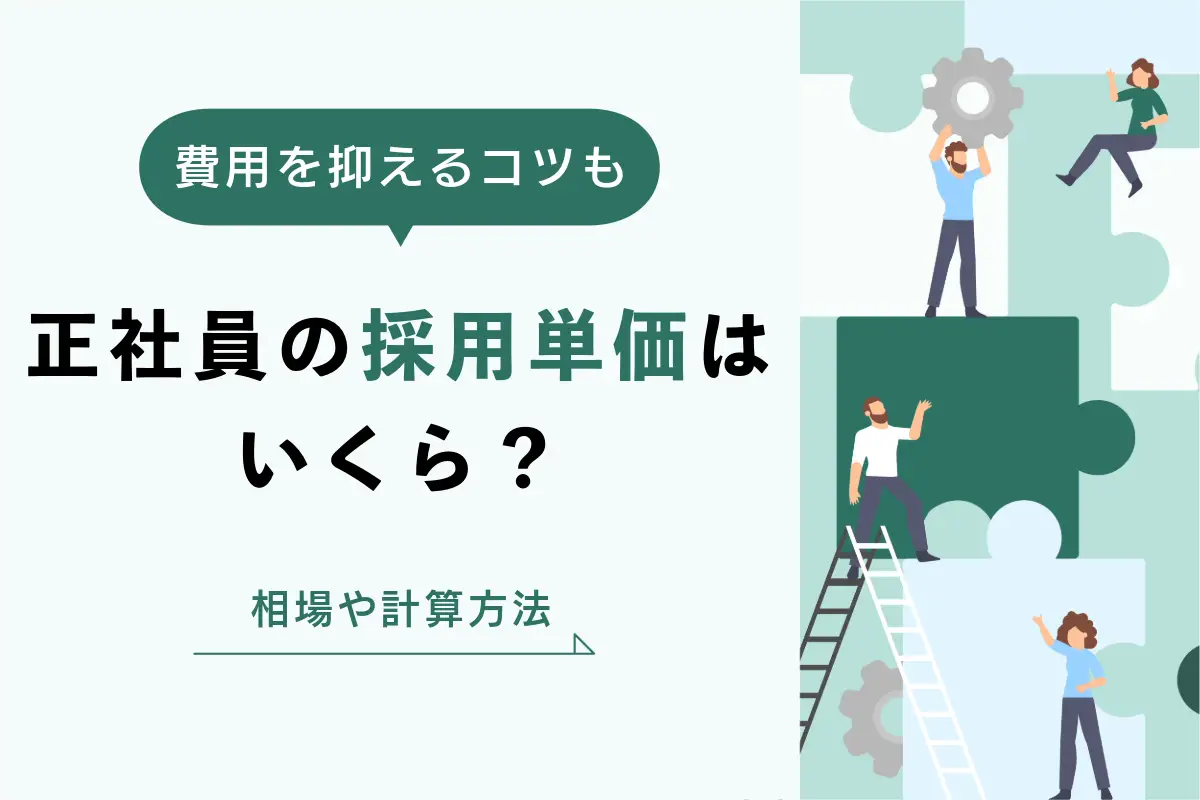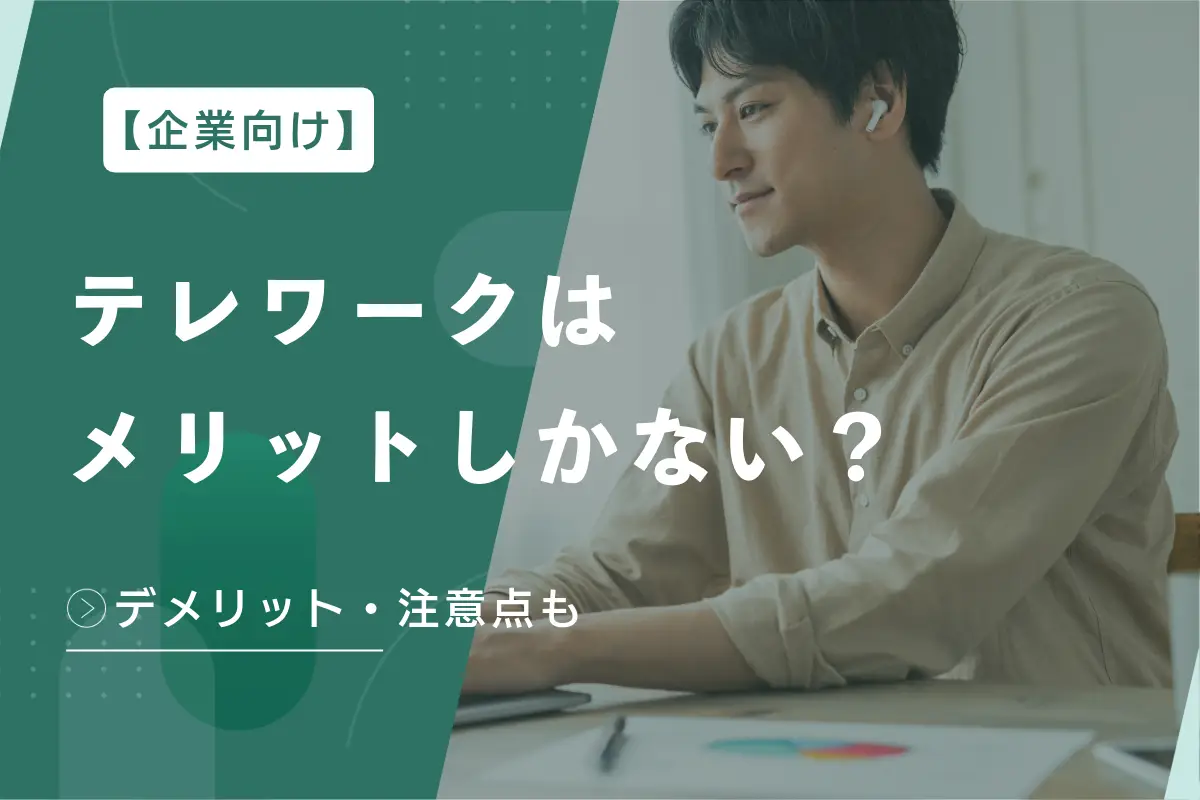「思った以上に採用コストがかかっている」「この採用単価は高すぎるのでは?」と感じたことはありませんか?正社員採用では、求人掲載費や採用担当者の人件費といったコストが発生します。経営リソースを圧迫しがちな採用単価ですが、「単価をただ抑えればいい」というわけではありません。
社員の早期離職が続けば、再び採用活動をしなければならず、結果的に費用が増大することもあります。そのため「なるべく採用単価を抑えたい」という場合、適正なコスト設定と、自社と相性のいい人材探しがキーポイントです。
そこで本記事では、正社員の採用単価の内訳や計算方法、採用単価の相場などを解説していきます。「自社の採用単価は相場と比較して妥当なのか判断したい」「採用単価を抑える方法を知りたい」という企業は、ぜひ参考にしてみてください。
正社員の採用単価とは?採用コストとの違い
「採用単価」とは、一人の正社員やアルバイトを採用する際にかかった費用の合計のことです。採用活動にかかった費用を、採用人数で割って算出されます。たとえば、年間の採用活動に300万円かかり、その期間で3人採用できた場合、採用単価は100万円となります。
一方「採用コスト」は、より広義な意味をもちます。母集団形成や書類選考、面接対応などにかかった人件費も含めたトータルコストを指すことが一般的です。つまり、「採用単価」は一人当たりにかかる採用コストであり、「採用コスト」は採用活動全体にかかる費用のこととなります。採用単価や採用コストの把握は、予算の調整や採用活動の改善・分析に役立ちます。
正社員の採用単価に関する具体的な内訳
正社員採用にかかる単価は、主に「内部コスト」と「外部コスト」に分けられます。以下でさらに詳しく解説していきます。
内部コスト
内部コストとは、採用活動を行う際に社内で発生するコストのことです。主に以下のような項目が該当します。
- 採用担当者の人件費(採用にかけた時間分の給与)
- 採用システムやツールの運用コスト
- 社内イベントで発生する費用(会場費など)
- 内定者の交通費 など
内部コストの多くは、応募者や内定者への対応業務に集中します。仮に内定辞退が発生すると再選考の対応が必要になり、スケジュール調整や面接準備にかかる社内工数が一気に増加するでしょう。こうした「やり直し」が、内部コストを押し上げる原因となります。
そのため採用単価を抑えるには、採用のミスマッチを防ぐ工夫が欠かせません。有効な方法のひとつに、「業務委託からの正社員登用」があります。これは、業務委託として実務に関わってもらった外部人材を正社員として採用する手法のことです。人柄や相性を確認した上での採用が可能なため、採用のミスマッチを防ぎやすい点が最大のメリットとなります。効率よく自社に合った人材を確保できるため、採用担当者の業務負担軽減と人件費の圧縮が期待できます。
外部コスト
外部コストとは、社外のサービスや媒体に支払う費用を指します。一般的な内訳は、以下の通りです。
- 求人媒体への掲載費(Web求人サイトや紙媒体など)
- 人材紹介会社への成功報酬
- 採用広報の制作費(パンフレット、動画、バナーなど)
- ダイレクトリクルーティングツールの利用料 など
外部コストは、金額が大きくなる傾向があります。特に、求人広告費や人材紹介費は高額になりやすいです。「掲載費無料の求人サイトの活用」や、「自社主体型のリファラル採用の導入」など、多様な方法で採用ターゲットを呼び込みましょう。
また外部コストは、費用をかけた分だけ必ず成果が出るとは限りません。そのため、施策ごとに「何に・いくら・どんな結果が出たのか」といった、定期的な振り返りと改善が重要です。適宜、採用プロセスを見直し、自社にとって最適な人材戦略を練っていきましょう。
正社員の採用単価・採用コストの計算方法
正社員の採用単価を把握するには、まず「何に・どれだけコストがかかっているか」を明確にすることが第一歩です。採用単価は、以下の式で算出できます。
採用単価 = 採用活動にかかった総費用 ÷ 採用人数
たとえば、求人広告に100万円、人材紹介手数料で200万円、社内工数の人件費に50万円で、合計350万円のコストがかかったとします。5人の正社員を採用した場合、採用単価は「70万円(=350万円 ÷ 5人)」です。
コストを算出すれば、自社の採用効率が見えてきます。計算結果が高いと感じたら、「どの費用がボトルネックになっているか」を分析してみましょう。採用コストの算出は、「内部コスト」と「外部コスト」の両面から調査します。
また、「広告費を抑えてリファラル採用を活用する」「作業を配分化させ業務委託を導入する」など、人材確保の方法を変えるだけでも採用単価を抑えられるケースもあります。現状の内訳を可視化させ、自社の採用活動を見直していきましょう。
正社員の採用単価の相場とは?種別ごとに解説
採用活動にかかる費用は、企業規模や業種、採用する人材のタイプによって異なります。そこでこの章では、「業界・職種別」「企業規模別」「新卒・中途」ごとに、正社員採用の相場を解説します。
【業界・職種別】正社員:採用単価の相場
企業規模や未経験採用・即戦力採用にもよりますが、採用単価は以下のように、業界や職種によってさまざまです。
| 区分 | 相場 |
| 例:営業職の場合 | 30万〜80万円程度 |
| 例:エンジニア・データサイエンティストの場合 | 100万円以上 |
また、高度なスキルを保有するIT・デジタル系の業界では、採用単価が100万円以上となるケースもあります。背景として、「人材の希少性が高さ」や「専門性の高さ」が起因しています。そのため、事前にターゲット人材の市場動向をリサーチした上で、採用単価の妥当性を確認していきましょう。
以下の記事では、外国人採用における採用コストについて解説しています。
参考記事:【特定技能外国人の受け入れ費用まとめ】費用相場もあわせて紹介|Jinzai Plus
【企業規模別】正社員:採用単価の相場
企業規模によっても、採用単価に違いが見られます。人材の市場価値や職種にもよりますが、大企業と中小企業の採用単価の相場は以下のとおりです。
| 区分 | 相場 |
| 大手企業の採用単価 | 50万〜80万円程度 |
| 中小企業やスタートアップ企業の採用単価 | 20万円程度 |
大手企業の場合、広告費や人材紹介への投資額が大きく、ブランド力や認知度を活かした採用活動を行う傾向があります。業種によっては100万円以上になることもあります。
中小企業やスタートアップ企業の場合、コスト調整がしやすい点から、業務委託を活用することも多いです。特にスタートアップ企業の場合、意思決定のスピードが速いため、多様な採用手法を積極的に導入する傾向があります。
【新卒・中途採用別】正社員:採用単価の相場
新卒と中途でも、以下のように採用単価の相場が異なります。
| 区分 | 相場 |
| 新卒採用の単価相場 | 50〜70万円程度 |
| 中途採用の単価相場 | 80万〜100万円程度 |
新卒採用は一括採用・集団選考が中心となるため、求人媒体や説明会などの初期投資が必要です。採用する業界や職種にもよりますが、一人あたりの単価は比較的低い傾向があります。
中途採用の場合は、人材紹介やスカウトといった外部サービスの活用率も高いため、採用単価が高くなりがちです。特に即戦力を求めるポジションでは、100万円以上必要になることもあります。新卒・中途、それぞれ採用戦略を分けて予算配分していくといいでしょう。
正社員の採用単価を抑える5つのコツ
ここでは、正社員の採用単価を抑える5つのコツについて紹介します。
正社員の採用単価を抑える5つのコツ |
|
1. ターゲットを明確にする
採用単価を下げるには、まず「どんな人を採用したいのか」といったターゲットの明確化が重要です。ターゲットが曖昧なまま求人を出すと、ミスマッチが増えて内定辞退や早期離職につながります。
また、スキルや志向性といった条件を具体化することで、より効果的な求人原稿を作成できます。再募集のコストを発生させないためにも、自社が求める人物像を明らかにしておきましょう。
2.採用チャネルを変更する
高額な人材紹介会社や求人広告に依存している場合は、一度チャネルを見直すことでコストを抑えられる可能性があります。特に即戦力を重視した中途採用では、業界や職種に特化した採用チャネルを活用すると、成果につながりやすいでしょう。
また、「初期費用が不要」かつ「成果報酬型のサービス」へのサービスに切り替えるといった対応も効果的です。さらに、返金保証制度のある紹介会社であれば、早期退職時のリスクを減らせます。
そのほか、社員紹介制度(リファラル採用)も有効です。紹介報酬を自社内で設定して社内で共有すると、外部コストを抑えつつ、信頼性の高い人材を確保できる可能性もあります。チャネルごとの費用対効果を分析し、自社に最適な方法を見極めていきましょう。
3. 採用手法を見直す
これまでの採用フローを見直すことも、単価を下げる有効な手段です。必要以上に手間のかかる選考プロセスを設けている場合、それが内部コストを押し上げている可能性があります。
たとえば「業務委託からの正社員登用」といった、段階的な採用プロセスを取り入れると、ミスマッチを防ぎつつ効率的な人材確保が実現します。これまで実績のある採用手法でも、変化の激しい市場に合わせて見直しを行うと、新たな改善点が見えてくるかもしれません。
▼関連記事:【企業向け】業務委託と正社員をどう切り替える?メリットや手続きの流れなど徹底解説
4.採用ブランディングを強化する
求職者に「この会社で働きたい!」と思ってもらえるよう、情報発信をしていきましょう。採用ブランディングが強化されると、自然と応募数が増え、紹介料や広告費だけに頼らない土台が整っていきます。
具体的には、社員インタビュー記事の公開、SNSでのカルチャー発信、自社サイトの採用ページの改善などが挙げられます。情報発信の強化によって、インターネット経由で自社に興味を持った人材からの応募を促進できます。
採用ブランディングは、継続することで効果を発揮します。そのため効果検証と改善を繰り返し、自社への関心層を日々増やしていきましょう。
5.内定後のフォローを徹底する
内定辞退や早期離職は、採用単価を押し上げる要因となります。費用と工数をかけて内定を出した人材が、入社に至らなかった場合の機会損失は大きいです。そのため、以下のような、内定後〜入社までのフォローが重要です。
- 現場社員とのカジュアル面談や懇親会
- 定期的なオンライン面談やメッセージのやりとり
- 入社前のオンボーディング施策(事前研修やeラーニング)
また、フォローの中で相互理解が進めば、ミスマッチによる辞退も防ぎやすくなります。採用単価だけでなく、教育コストやチーム全体の生産性低下を防ぐ意味でも、フォローは必要です。
採用は内定を出して終わりではなく、「入社後の活躍」までを見据えた長期的なプロセスです。入社前から丁寧なフォローを行い、優秀な人材を無理なく定着させられる体制を整えていきましょう。
正社員の採用単価だけにこだわると危険な理由
採用単価を抑えることは、もちろん経営的に重要な視点です。しかし「とにかく安く採用したい」という視点ばかりに固執すると、かえってコストが膨らむこともあります。
たとえば、ミスマッチによる早期離職や社内の生産性低下など、「見えない損失」として企業に大きなダメージを与えることがあります。これらは一度発生すると取り戻すのに時間とコストがかかるため、結果的に採用単価以上の負担となりかねません。そこでこの章では、正社員の採用単価だけにこだわると危険な理由について解説していきます。
早期離職で「再雇用+教育」の二重コストが発生するから
採用単価だけを重視してコストを抑えた結果、自社に不一致な人材を採用してしまうと、早期離職へのリスクが高まります。求人掲載や選考をやり直す必要があり、新たな採用コストが発生します。
さらに、離職した社員に実施した教育や、研修コストも無効になります。「採用コスト+教育コスト」の二重負担を考えると、単価の安さだけで判断するのはリスクが大きいといえるでしょう。
社内の生産性低下につながるから
採用単価を最優先にしすぎると、本来求めているスキルや、カルチャーフィットの基準に満たない人材を無理に採用してしまうかもしれません。結果的に、「ミスやトラブルの増加」「既存社員の意欲低下」といった事態に発展する可能性もあります。
そのため採用コストだけでなく、「長期的に活躍してくれる人材か?」「自社のビジョンや雰囲気にマッチする人材か?」という視点での選考が重要です。
企業の信頼やブランド価値を損なう可能性があるから
人材の辞職が続くと、「この会社は入社後にミスマッチが多い」「職場環境が悪いのでは?」といったネガティブな印象を外部に与える可能性があります。
最近では転職のクチコミサイトやSNSを通じて、企業の評判がすぐに広まります。一度悪評が広まれば、優秀な人材の応募が減るだけでなく、既存社員のモチベーション低下や離職にもつながりかねません。
採用単価ばかりに集中し、会社として「人材を大切にする姿勢」が伝わらなければ、信頼を損ねる結果になります。そのため、採用活動を企業ブランディングの一環として捉え、採用の精度を高めていきましょう。
▼関連記事:業務委託と正社員、どっちがいい?両者のメリットや正社員転換のステップまで解説
フリーランス人材を正社員として迎える3つのメリット
近年、フリーランスとして一定期間業務に携わった人材を、正社員として登用する企業が増えています。この採用手法は、事前にスキルや相性を見極められるため、ミスマッチの防止につながります。従来の採用活動で必要だった広告掲載費といったコストを削減できる点でもメリットです。
ここでは、フリーランス人材を正社員として迎えるメリットについて紹介します。
フリーランス人材を正社員として迎える3つのメリット |
|
1. 採用単価や人件費の抑制が期待できる
フリーランス人材を正社員化する手法は、採用単価を抑えたい企業に有効です。たとえば、広告掲載費といった外部コストを削減できます。
また、フリーランスとの契約期間中は、業務に応じたプロジェクト単位での報酬支払いとなるため、固定の人件費を抱えずに済みます。「必要な時に・必要な範囲で依頼できる」柔軟性は、採用リスクの分散にもつながるでしょう。採用にかかるコストと時間を短縮しつつ、即戦力人材を確保できます。
2. スキルや協調性を見極めた上での採用が可能
フリーランスとして一定期間業務を委託することで、実際の働きぶりや社内との相性を見極めた上で、正社員登用を判断できます。履歴書や面接では把握しきれない、「業務スキル・人間性・価値観」を確認できる点が、この手法の大きな強みです。
たとえば、タスクの進め方やフィードバックへの反応などは、一緒に仕事をして初めて見える要素です。こうした定性的な情報を事前に確認できることで、採用判断の精度が格段に高まります。また、入社前の関係構築や業務連携によって、オンボーディングや研修もスムーズです。企業は、候補者による早期活躍と長期的な貢献が期待できます。
3.定着率の向上が見込める
フリーランスから正社員へと進める段階的な採用プロセスは、信頼関係を自然に育むことができるため、高い定着率につながります。業務委託期間中に、仕事内容やチームの雰囲気、評価制度などを体験できるため、入社後のギャップを最小限に抑えられます。
また、仕事内容やカルチャーを十分に理解した上での意思決定となるため、受け身の入社ではなく、候補者の主体的な働き方が期待できます。さらに、前向きな動機で入社した人材は離脱しにくく、自らの役割を自覚した上でパフォーマンスを発揮しやすいです。企業はモチベーションの高い人材を迎えられ、チームや成果にも好影響となるでしょう。
▼関連記事:【企業向け】フリーランスと正社員の違いとは?両者のメリットや注意点など徹底解説
採用のミスマッチを減らしたい企業は『Workship CAREER』がおすすめ!
ここまで、採用単価の内訳や相場、コストを抑える具体的な工夫など、解説してきました。人材採用では単に採用費用を削るのが正解ではなく、「採用の精度を高めて成果につながる人材を迎えること」が最も重要です。
しかし実際には、「コストをかけてもミスマッチが起きる」「採用のプロセスに時間もリソースも割けない」といった悩みを抱えている企業も少なくありません。そんなときに頼れるのが、人材紹介エージェントの『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』です。
Workship CAREERでは、ハイスキルなIT・Web系人材を迅速にご提案いたします。企業文化や募集背景に応じた人材紹介や、業務委託から正社員化の打診など、マッチング精度の高い採用を支援いたします。
Workship CAREERの特長
- トランジション採用の導入:業務委託契約からスタートし、その後正社員登用への切り替えを支援いたします。
- 豊富な人材データベース:エンジニア、デザイナー、PMなど、約5万人以上のフリーランスネットワークから、企業のニーズに合った候補者をご紹介いたします。
- 人事のプロが採用から育成まで一貫して伴走:定例会議やスポット対応など、貴社の人事課題をトータルに解決いたします。
「正社員採用の効率を見直したい」「今より質の高い採用活動がしたい」とお考えの企業は、一度Workship CAREERにご相談ください。
Workship CAREERでは、貴社の採用課題や募集内容をヒアリングした上で、最適な人材をご紹介いたします。無料相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。
- Workship CAREERのサービス内容
- ご契約の流れ
- 取引実績
- 関連サービス

リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェント「Workship CAREER」の編集部です。採用に役立つ情報を発信していきます。