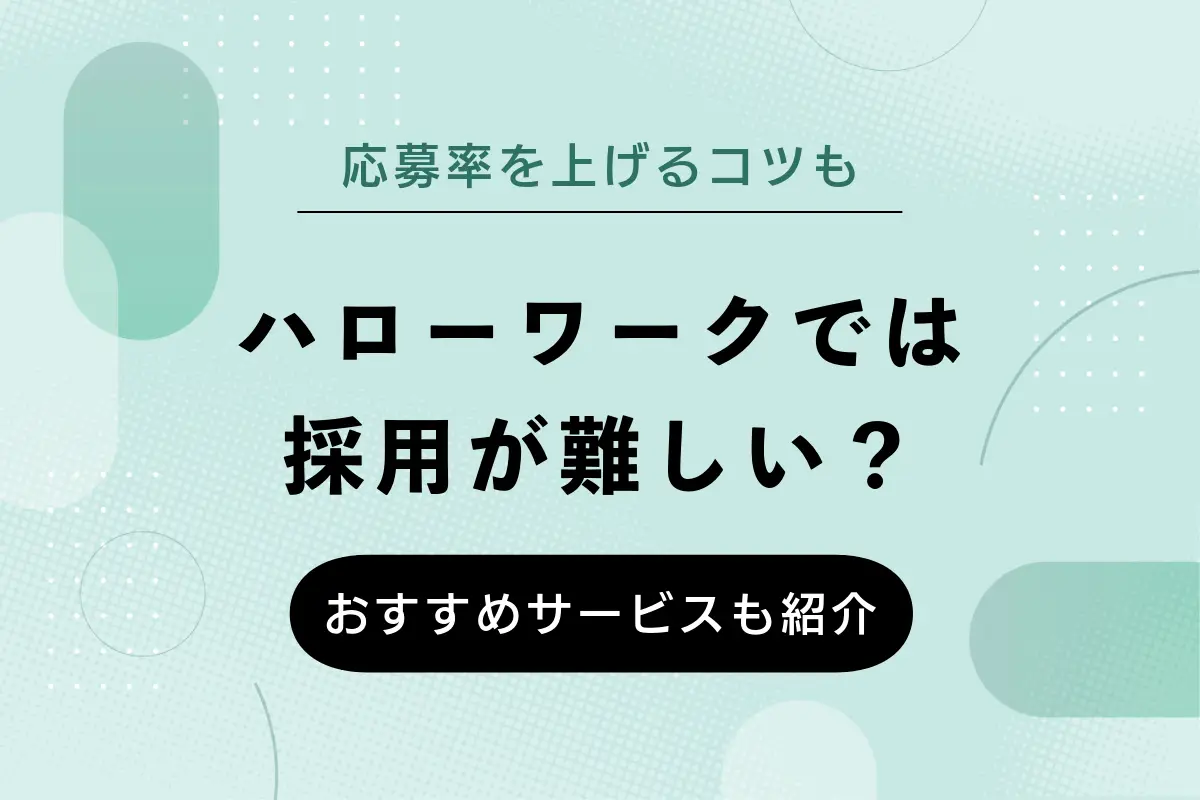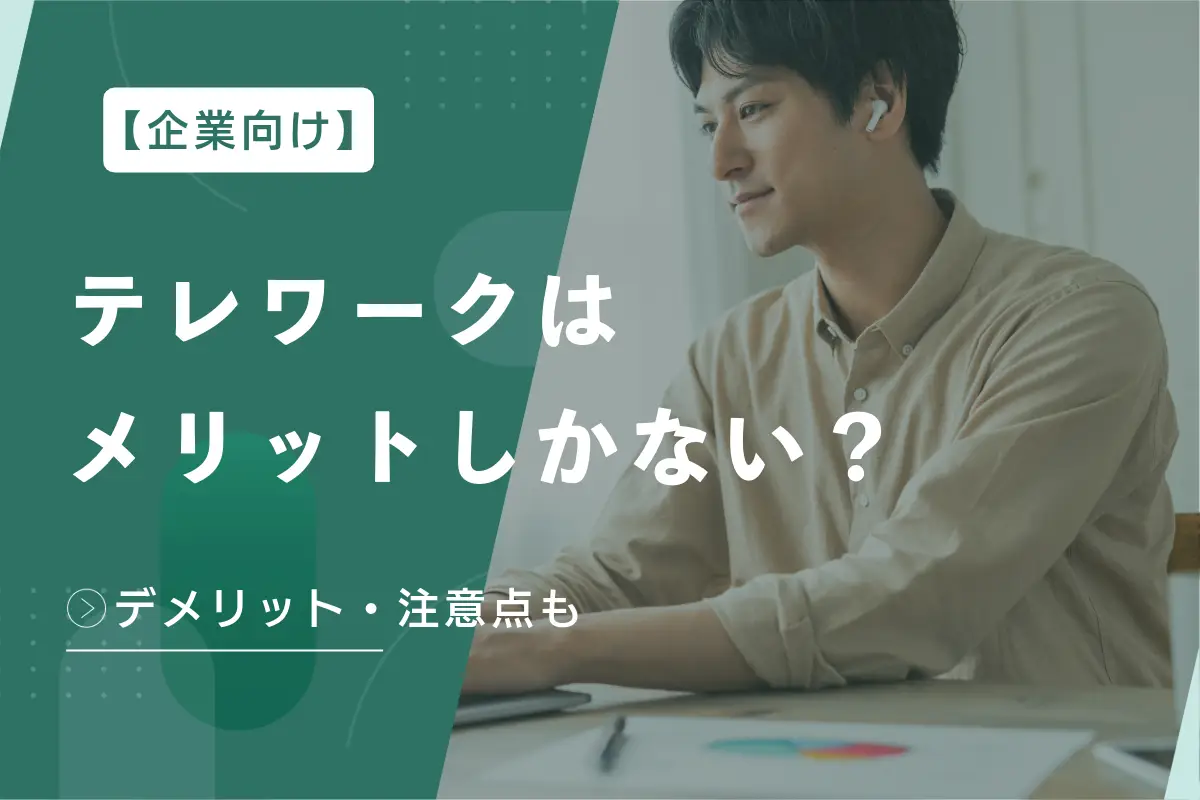「ハローワークに求人を出しても応募がこない」「なかなか候補者が見つからない」と悩んでいませんか?ハローワークを活用すると、掲載費用をかけず幅広い属性の求職者とつながれます。
しかしハローワーク経由で採用活動を成功させるには、採用ブランディングの強化や応募後のフォローといった対策や配慮が欠かせません。
本記事では、ハローワーク経由で採用が難しい理由や応募率を上げるコツ、ハローワークと併用すべき人材採用の手法など解説していきます。現在「ハローワークを使って採用活動を進めている」という企業だけでなく、今後「ハローワークの活用を検討している」という企業もぜひ参考にしてみてください。
ハローワークでは採用が難しい?考えられる4つの原因
ハローワークに求人を掲載したものの、「応募が来ない」「面接しても自社に合う人材と出会えない」と感じている企業は少なくありません。
ここでは、「ハローワークでの採用が難しい」と企業が感じる原因について深堀りしていきます。
1.ハローワークの利用者が減ってきているため
ハローワークでの採用が難しい原因の一つに、ハローワークの利用者の減少が挙げられます。厚生労働省の調査(以下データ)によると、パートタイムを含む「新規求職申込件数」が年々減少していることがわかります。
出典:厚生労働省-公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績
利用者減少の背景として、以下のような点が考えられます。
- 少子高齢化による労働者人口の減少
- フリーランスや副業といった働き方の多様化
- インターネットを活用した求人募集の普及
- 民間求人サービスの増加
こうした時代の流れや変化に伴い、ハローワークを活用した人材採用は、これまでよりも難しくなっています。
2.企業独自の採用戦略が取りにくいため
ハローワークは、求職者に広く平等な雇用機会を提供する、公的な職業紹介サービスです。そのためターゲットの絞り込みや、採用ブランディングの実施など、戦略的な採用活動はしにくいでしょう。
たとえば、求人票のフォーマットは定型化されており、掲載できる情報量や内容に制限があります。検索機能やデザインもシンプルであるため、自社の求人が求職者の目に留まりにくいです。また、数ページにもおよぶ企業紹介や、社員紹介インタビューの記事掲載など、企業の個性や魅力をアピールするのは難しくなっています。
企業独自の採用戦略が取りにくい背景から、ハローワークでは「応募が集まらない」「採用に至らない」となりやすいでしょう。
3.応募へのハードルが高いため
ハローワーク経由での応募は、求職者にとって手間がかかりやすく、応募までのハードルが高いことが指摘されています。たとえば求人に応募したい場合、求職者はハローワークに出向いて「紹介状」を発行してもらう必要があります。特に「複数の企業から話をすぐに聞きたい」「早く応募して採用まで進みたい」というニーズが強い人は、このフローを面倒だと感じるケースが多いです。
またハローワークの求人票は掲載できる情報が限定的なため、求職者が「働くイメージがしにくい」と感じ、応募をためらいます。このようにハローワーク経由での応募は、物理的・心理的なハードルが複数存在するため、結果「求人掲載しているのに応募がこない」という事態になりやすいです。
4.ハローワークの担当者による支援が限定的なため
ハローワークの担当者は、多くの求人企業と求職者を同時に支援しているため、企業ごとにきめ細かくフォローするのが難しいです。提供されるサポートの多くは、求人票の記載内容に関するチェックや、助成金制度の一般的な案内など、マニュアル的な対応にとどまりやすい傾向があります。
仮に求人掲載後に応募がなかったとしても、「しばらく様子を見ましょう」といった反応にとどまり、原因分析や改善提案までは踏み込みません。このように、ハローワークでは採用活動を能動的に後押しするわけではないため、企業は人材採用が難しいと感じるでしょう。
ハローワークを活用するメリット
「採用が難しい」と言われているハローワークですが、いくつかメリットもあります。ここでは、ハローワークを活用するメリットについて解説していきます。
無料で求人を掲載できる
ハローワークの最大のメリットは、求人掲載に費用がかからないことです。成功報酬や応募課金といったコストが一切発生しないため、採用予算に限りがある中小企業や個人事業主でも手軽に利用できます。
また更新の手続きをすれば、長期間の掲載も可能なため、常時人材を募集していたい場合にも有効です。「初期投資を抑えつつ、応募の間口を広げたい」と考える企業には、特にメリットが大きいでしょう。
地域に特化した採用活動が可能
ハローワークは全国に拠点を持つ、地域密着型の公的機関です。「地元で働きたい」と考える求職者が多く利用しているため、地方志向の人材との出会いが期待できます。
また、地域の労働市場に精通したハローワークの職員と連携すると、有益な情報を提供してもらえるかもしれません。さらに、ハローワーク主催の企業説明会やイベントに参加すると、求職者と直接関わることもできます。地域に特化した採用活動により、エリア内での企業の認知度も向上していくでしょう。
幅広い属性の求職者と接点が持てる
ハローワークは、若い世代から中高年、主婦層まで、年齢やライフスタイルに関係なく、さまざまな人が利用しています。また、なかには「すぐに転職しないが、情報収集のために立ち寄っている」という人も多くいます。さらに、失業手当の手続きや職業訓練の申込みのついでに、求人情報を見るケースも少なくありません。
こうした「幅広い背景を持つ人に、自社の求人を見てもらえる」という点で、ハローワークは将来の応募につながる「企業の認知拡大の場」としても活用できます。「とにかく人手がほしい」「幅広い層の人材を採用したい」という企業には、ハローワークが心強い採用チャネルとなるでしょう。
採用に関する行政支援が受けやすい
ハローワークは、単なる求人情報の掲示板ではなく、厚生労働省が運営する公的な雇用支援機関です。企業は、採用に関するさまざまな行政支援や制度の案内を受けられます。以下では、代表的な支援制度についてまとめました。
支援制度名 | 内容・対象 |
トライアル雇用助成金 | 求職者を一定期間、試験的に雇用した際に支給される助成金。 |
人材確保等支援助成金 | 職場環境改善や業務負担軽減に取り組む企業への助成金。 |
地域雇用開発助成金 | 特定地域で事業所を新設・拡張した際に支給される助成金。 |
雇用調整助成金 | 経済的理由で一時的に雇用維持が困難な場合の休業・教育訓練等に対して支給される助成金。 |
ハロートレーニング | 公共職業訓練(主な対象:雇用保険の受給者)と求職者支援訓練(主な対象:雇用保険を受給できない求職者)の提供。 |
マザーズハローワーク | 子育て中の女性を対象にした採用活動支援。 |
外国人雇用サポート | 外国人採用に関する情報提供・相談、求人票の多言語対応など。 |
出典:厚生労働省: 雇用関係助成金一覧 / ハロートレーニング / ハローワーク
たとえば「トライアル雇用助成金」では、特定の条件を満たす人材を採用すると、企業は助成金を受け取れます。こうした制度をうまく活用すれば、採用にかかる負担を抑えつつ、多様な人材の受け入れを進められるでしょう。
また採用後の人材育成や定着も、ハローワークによって支援してもらえることがあります。そのため安定的な組織づくりを目指す企業にとって、充実したサポート体制のハローワークを活用するメリットは大きいといえるでしょう。
ハローワークのデメリット
では反対に、ハローワークのデメリットも見ていきましょう。
採用のミスマッチが起きやすい
ハローワークの求人票では、フォーマットに沿ったシンプルなものになるため、企業の魅力や業務の詳細を十分に伝えにくいです。その結果、求職者が仕事内容や職場の雰囲気を正確にイメージできず、「思っていた仕事・職場と違った」と感じやすいでしょう。
またハローワークを利用する求職者の中には、緊急的に仕事を探している人や、希望条件がまだ固まっていない人も多いです。十分な情報収集や自己分析を経ずに応募してくるケースもあるため、マッチング精度がやや低くなる傾向があります。求職者と企業側の間で認識のズレが生じやすい点は、ハローワークのデメリットとなります。
空求人やブラック求人と並列表示される
ハローワークは無料で求人を掲載できる反面、「空求人」や「ブラック求人」と呼ばれる案件も載っていることがあります。「空求人」と「ブラック求人」の意味は、以下の通りです。
名称 | 意味 |
空求人 | 企業側が「採用する意思がない」または「すでに採用を終了しているのに求人を取り下げていない」など、形式上だけ掲載している求人のこと。 |
ブラック求人 | 過重労働・低賃金・労働環境が劣悪など、法令違反やコンプライアンスに抵触する恐れのある求人のこと。 |
このような「質の低い求人」が同じプラットフォーム上に混在していると、ハローワーク全体のイメージが悪くなり、他の誠実な企業にも悪影響です。
求職者の中には、「ハローワークの求人は信用できない」「条件と実態が違うことが多い」と感じ、応募を敬遠している人もいます。応募者の質や数に影響を与える可能性がある点は、ハローワークの短所といえるでしょう。
手続きにやや手間がかかる
ハローワークで求人を掲載する際は、求人票の作成・提出といった各種手続きを基本的に窓口で行う必要があります。オンラインで完結できる民間の求人媒体と比べ、必要書類の準備や記入方法の確認に時間を要することが多いです。
また、求人票を修正・更新したい場合も、反映までに数日かかることがあり、タイムリーな情報発信や細かな改善もしにくいです。手続きの自由度やスピード感に欠ける点は、ハローワークのデメリットとなります。
ハローワーク経由で応募率を上げる5つのコツ
ハローワークで応募率を上げるには、求人の出し方や対応の仕方で改善できます。ここでは、ハローワーク経由で応募率を上げる5つのコツを紹介します。
1.求人票に情報を明確に記載する
ハローワークの求人票があいまいな情報提示だと、求職者が不安を感じて応募をためいます。そのため、業務内容や働く環境といった情報を、数値を交えて具体的かつ正確に記載しましょう。以下はその一例です。
仕事内容 | 良い例 |
接客・販売 | 「洋服が好き、人と話すのが好きな方にぴったり!未経験から始められる接客・販売のお仕事です。20〜30代女性が中心の明るい職場です。」 |
一般事務 | 「電話応対やデータ入力が中心のシンプルな事務作業です。PCの基本操作ができればOK!丁寧なOJTで未経験でも安心してスタートできます。」 |
医療・介護系 | 「利用者様と笑顔で過ごせるあたたかな職場です。日勤のみ・残業ほぼなし。未経験・無資格の方も歓迎、丁寧にサポートします。」 |
営業職 | 「既存のお客様へのフォロー営業が中心。飛び込みなしで安心!人と話すのが好きな方、営業デビュー歓迎です。」 |
保育士 | 「子どもが好きな方大歓迎!のびのび保育を大切にする少人数制の園です。職員同士のチームワークも良好◎」 |
上記のように記載すると、「自分に合っていそう」と感じてもらいやすくなり、応募率の向上につながります。
また、ネット上でのハローワークの求人一覧では「仕事内容」は最初の3行ほどしか表示されません。数ある求人の中で目に留まってもらえるよう、冒頭で興味を引く言葉や表現を入れて文章を作成していきましょう。
参考:ハローワーク新発田
2.採用ブランディングを強化する
ハローワークの求人では、企業のカラーが出しにくいです。そのため自社の魅力が伝わるよう、採用ブランディングを強化させましょう。たとえば、以下のような方法が有効です。
採用ブランディングの方法 | 詳細・内容 |
自社サイトに採用ページを設置する | 仕事内容や社員インタビュー記事などを掲載 |
SNSを運用する | 企業の雰囲気や日常、社員の声などを日々発信する |
採用サイトやパンフレットに載せる、スローガンやロゴを統一する | 働き方や価値観を端的に表現する言葉や、企業のロゴ、色合いを統一させてオリジナリティを出す |
採用マーケティングでは、言葉や情報の見せ方など、記憶に残る印象づけが重要です。また、「採用専用ページのリンクを添付して求職者に詳細情報を読んでもらう」といった導線設計も欠かせません。SNSや自社メディアを活用し、応募者に好印象を与える採用戦略を展開していきましょう。
3.ハローワークの担当者と連携する
多くのハローワークの担当者は、地域の求人動向や求職者のニーズを把握しています。企業が求める人材像や業務内容を丁寧に伝えておくと、担当者から有益なアドバイスを提供してもらえるかもしれません。
また担当者と信頼関係を築いておくと、職業相談の場で求職者に自社求人を積極的に紹介してもらえる可能性が高くなります。地域の採用パートナーとなる、ハローワークの担当者と協力して採用活動を成功させましょう。
4.応募への負担を減らす
ハローワーク経由の応募は、基本的に「紹介状を発行してから応募書類を送付する」という流れが必要です。求職者によってはこのフローを「手間がかかる」と感じるため、少しでも応募までのハードルを下げる工夫が欠かせません。たとえば以下のように、応募への負担を下げる工夫をしましょう。
- 履歴書の手書きを求めず、PC作成を認める
- 職務経歴書のフォーマットを指定しない
- 面接日程を適宜調整する
また、求人票に「未経験歓迎」「事前見学OK」などの文言を入れると、行動を迷っている求職者の背中を押すことができます。自社の採用基準を維持しつつ、可能な範囲で柔軟な姿勢を見せていき、応募数を増やしていきましょう。
5.応募後のフォローを徹底する
応募者の離脱を防ぐためにも、迅速かつ丁寧な対応が重要です。たとえば、以下のような小さな心配りが応募者に安心感を与えます。
- 応募書類が届いたらすぐに受領の連絡を入れる
- 面接日程の案内をスムーズに行う
- 面接前に業務内容や職場の雰囲気をあらためて伝える
ハローワークを利用する求職者の中には、就職活動に不安を抱えている人や、ブランクのある人もいるため、企業側が積極的にコミュニケーションを取ることで信頼を得やすくなります。選考過程では誠実な対応を心がけ、入社までつなげていきましょう。
ハローワークと併用したい!人材採用の手段
ハローワークは公的機関ならではの信頼性と幅広い求職者層へのアプローチが可能な反面、「情報発信の自由度が低い」「即戦力人材との接点が少ない」などの課題もあります。そこで効果的なのが、ハローワークと他の採用チャネルとの併用です。
民間の求人媒体やエージェントなどを組み合わせると、求職者との接点を広げるだけではなく、自社にマッチした人材との出会いの精度も高められます。ここでは、ハローワークと併用しやすい代表的な採用手段をいくつかご紹介します。
求人サイトへの掲載
求人サイトは、業種・職種・勤務地・雇用形態などの条件で絞り込んで探せるため、求職者にとって使いやすいツールです。企業側にとっても、写真やキャッチコピーなどを活用して自社の魅力を視覚的・戦略的にアピールできる点が大きな強みです。代表的なサービスには、以下のようなものがあります。
サービス名 | ターゲット層 | 特徴 |
リクナビNEXT | 20〜40代の転職希望者 | 国内最大級/転職意欲の高い層 |
マイナビ転職 | 若手社会人・地方の人材 | 地方採用に強い/新卒との連携も可 |
doda | 20〜40代の正社員志望層 | 転職エージェントとの併用可能 |
エン転職 | 若手・第二新卒層に強い | 丁寧な求人情報・口コミ重視 |
また求人サイトの多くは、スマートフォンに最適化されており、通勤中やスキマ時間に求人をチェックしている層へのリーチにも優れています。比較する際は、求人掲載料や期間、特徴を確認しながら、自社に合ったサイトを選びましょう。
転職エージェントの活用
転職エージェントは、採用のプロであるキャリアアドバイザーが間に入り、企業と求職者のマッチングをサポートするサービスです。特に「即戦力人材を早く採用したい」「条件に合う人材がなかなか見つからない」といった課題を抱える企業にとって有効な手段となります。以下では代表的なサービスをまとめました。
サービス名 | ターゲット層 | 特徴 |
リクルートエージェント | 20代〜40代の幅広い層 | 業界最大級の登録者数/提案力が高い |
マイナビエージェント | 20代〜30代の若手人材 | 若年層採用に強い/丁寧なサポート |
パソナキャリア | 30代〜40代の幅広い層 | 対応が丁寧/女性管理職の紹介実績も多い |
転職エージェントを活用すると、企業の採用ニーズから、条件に合致する求職者を厳選して紹介してもらえます。また、求職者との面談や日程調整、条件交渉なども代行してくれるため、採用担当者の負担軽減にもつながります。ただし、費用体系が成功報酬型で高額になるケースもあるため、注意しましょう。
ビジネスSNSの利用
ビジネスSNSは、職務経歴やスキルを登録したビジネスパーソンと直接つながれる、採用チャネルの一つです。求職活動中でない潜在層にもアプローチできるため、希少性の高い専門人材やハイクラス層にもリーチできます。代表的なサービスは以下の通りです。
サービス名 | ターゲット層 | 特徴 |
ハイクラス人材・グローバル層 | グローバル対応/ダイレクト採用に強い | |
Wantedly | 若手・ベンチャー志向の層 | カルチャーフィット重視/発信型採用 |
ビジネスSNSでは、企業のビジョンやカルチャーをコンテンツとして発信できるため、採用ブランディングの強化にもつながります。一方で、活用にはノウハウや運用コストが必要です。
ダイレクトリクルーティングを取り入れる
ダイレクトリクルーティングとは、企業が求職者に直接アプローチして採用につなげる手法のことです。従来の「応募を待つ」スタイルとは異なり、スカウトメールやSNSを通じて、自社にマッチしそうな人材へ声をかけます。以下では、代表的なサービスをまとめました。
サービス名 | ターゲット層 | 特徴 |
ビズリーチ | ハイクラス・即戦力層 | 高年収層が中心/企業からスカウト可能 |
ミイダス | 幅広い職種の中途人材 | 適性診断連携/スカウト送付数は無制限 |
ダイレクトリクルーティングでは、転職潜在層や他社で活躍している即戦力人材にもアプローチできます。ハローワークだけでなく、ダイレクトリクルーティングのような戦略的アプローチも併用していきましょう。
リファラル採用を進める
リファラル採用とは、自社の社員からの紹介を通じて人材を集める採用手法のことです。紹介者と候補者の間に信頼関係があるため、採用後のミスマッチが起こりにくく、定着率が高い傾向があります。リファラル採用したい場合は、以下のようなサービスを活用してみましょう。
サービス名 | ターゲット層 | 特徴 |
YOUTRUST | スタートアップ/IT/若手層 | ビジネスSNS型/つながり経由のスカウトが可能 |
Eight Career Design | 転職潜在層/Eightユーザー | 名刺管理アプリ「Eight」と連携可能/ダイレクトリクルーティングも可能 |
Refcome | 全業種対応/中小〜大手企業 | リファラル特化型クラウドツール提供やRPOサービスを展開 |
リファラル採用は求人広告費がかからないため、採用コストを抑えられます。社員の知人や元同僚など、「求人に応募しようとは思っていなかった潜在層」にもリーチできるため、他の採用手段では出会えない人材を確保できるかもしれません。
ただし、紹介してもらった人材を不採用したい場合は注意が必要です。不採用の経緯や理由を説明し、不和が起きないように対応していきます。また、社員に積極的に協力してもらうためにも、リファラル採用のメリットや仕組みを伝え、人材紹介しやすい環境にしていきましょう。
フリーランス・副業人材の紹介サービスを使う
近年、正社員にこだわらず、フリーランスや副業人材に仕事を依頼する企業が増えています。特にITやクリエイティブ、マーケティング分野など、専門スキルが求められる業務で活用が進んでいます。以下では、代表的なフリーランス・副業人材を紹介するサービスについてまとめました。
サービス名 | ターゲット層 | 特徴 |
即戦力のフリーランス人材を紹介/正社員登用の打診が可能 | デザイン/開発/マーケティング | |
ITプロパートナーズ | 週2〜3日稼働のITフリーランスが豊富/エンジニア・デザイナーに強い | IT・Web系/スタートアップ |
シューマツワーカー | 週末・副業ワーカーが中心/リモート案件に対応 | Web系スタートアップ/副業特化 |
上記のようなサービスを活用すれば、企業のニーズに合ったスキルや経験を持つ人材を迅速に紹介してもらえます。ハローワークだけでは出会いにくい外部の専門人材とつながれる点は大きな魅力です。
また業務委託契約の場合、繁忙期・閑散期など時期に応じて案件や仕事を依頼できるため、コスト調整もしやすいです。特に、新規事業の立ち上げやプロジェクトベースの業務では、正社員採用に伴うリスクを抑えながら人手を補強できます。採用の幅を広げる手段として、業務委託も検討してみましょう。
▼Workshipのサービス概要は、以下からダウンロードできます

「業務委託から正社員登用」をおすすめしたい3つの理由
正社員採用は、長期的な人材確保において理想的な手段ですが、最初からミスマッチのない人材を見つけるのは簡単ではありません。そこで近年注目されているのが、「まずは業務委託として働いてもらい、双方が納得した上で正社員登用につなげる」という採用手法です。
フリーランスや副業人材を正社員登用する方法は、定着率の向上と採用リスクの低減が期待できます。ここでは、「業務委託から正社員登用」をおすすめする理由をご紹介します。
1.採用のミスマッチを防げるから
正社員採用では、書類選考や数回の面接だけで採否を判断するため、スキル面やカルチャーフィットのズレが後からわかることも少なくありません。
一方、業務委託として一定期間働いてもらうことで、実際のスキルや仕事への取り組み方、社内メンバーとの相性などを確認できます。定性的な部分のミスマッチを大幅に減らせる点は大きなメリットです。
また求職者側も、「この会社で長く働けそうか?」「仕事内容や職場の雰囲気が合っているか?」など、判断・納得したうえで入社を決断できます。このように企業と求職者の双方に「見極めの期間」があると、定着率の向上につながります。
2.採用コストを最小化できるから
求人サイトや転職エージェントを活用して正社員を採用すると、求人広告費や人材紹介料といったコストが発生します。仮に採用した人材が早期離職すれば、一から採用活動を再開する必要があり、費用負担が増えます。これは特に、スタートアップ企業や中小企業にとって大きな痛手となるでしょう。
一方、業務委託の場合、プロジェクト単位や期間単位での契約が可能です。経費項目は「外注費」となり、スポット的に活用できます。
業務委託から正社員登用する方法を導入すれば、段階的な信頼関係の構築で、候補者と企業の双方が相性を見極められます。結果、納得度の高い採用となることで定着率が向上し、採用活動にかかるコストの余剰を抑えられるでしょう。
3.ハローワークにいない即戦力人材と出会えるから
ハローワークの場合、利用者の属性が幅広く、「今すぐ仕事したい」というニーズが強い人が集まります。
一方、業務委託の場合、「副業・フリーランスとして実績を積んできた」「自分のスキルを活かせる機会があれば挑戦したい」と考える即戦力が多くいます。特に、専門スキルを持ったエンジニアやマーケター、デザイナーなどは、ハローワークには登録していない人も多いです。業務委託というアプローチから入ることで、他の求人サイトやエージェントにはいない、優秀な人材とのマッチングできるチャンスが広がります。
▼関連記事:【企業向け】業務委託と正社員をどう切り替える?メリットや手続きの流れなど徹底解説
採用のミスマッチを減らしたいときは『Workship CAREER』におまかせ!
ハローワークは、無料で求人を掲載できる・地域に根ざした採用ができるといった利点があります。その一方で、ミスマッチの発生や情報発信の制限、応募のハードルの高さなど、採用における制約も少なくありません。
特に、専門スキルを持つ即戦力人材や、カルチャーフィットする人材をスピーディーに採用したい場合、ハローワークだけに頼るのは非効率です。
そんな課題を感じている企業におすすめなのが、フリーランス・副業人材に強い転職サービス『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』です。Workshipキャリアでは、週2〜3日の業務委託からスタートし、実際に働いた後に正社員としての登用も可能。現場との相性やスキル適性を見極めながら、ミスマッチの少ない採用が実現できます。
また、登録している人材はIT・Web・クリエイティブ・マーケティングなどの即戦力層が中心。求人掲載や人材採用に関するサポートも充実しており、初めての企業様でも安心して導入できます。
Workship CAREERの特長
- トランジション採用の導入:業務委託契約からスタートし、その後正社員登用への切り替えを支援いたします。
- 豊富な人材データベース:エンジニア、デザイナー、PMなど、約5万人以上のフリーランスネットワークから、企業のニーズに合った候補者をご紹介いたします。
- 人事のプロが採用から育成まで一貫して伴走:労務管理や育成制度設計など、貴社の人事課題をトータルに解決いたします。
ハローワークだけでは出会えない優秀な人材と、まずは「業務委託」でつながってみませんか?Workshipキャリアでは、貴社の採用課題や募集内容をヒアリングした上で、最適な人材をご紹介いたします。無料相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。
▼Workshipキャリア:サービス資料のダウンロードはこちらから

なお、「まずは業務委託でスキルを見極めたい」「副業・フリーランス人材に仕事を依頼してみたい」という企業様には、即戦力人材と即日マッチングできる「Workship」もおすすめです。
Workshipでは、専任のカスタマーサクセスが、貴社の条件にあった候補者を随時ご提案いたします。スタートアップから中小企業・大手企業の新規事業まで、多くの企業で導入が進んでいます。お気軽にお問い合わせください。
▼Workship:サービス資料のダウンロードはこちらから

- Workship CAREERのサービス内容
- ご契約の流れ
- 取引実績
- 関連サービス

リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェント「Workship CAREER」の編集部です。採用に役立つ情報を発信していきます。