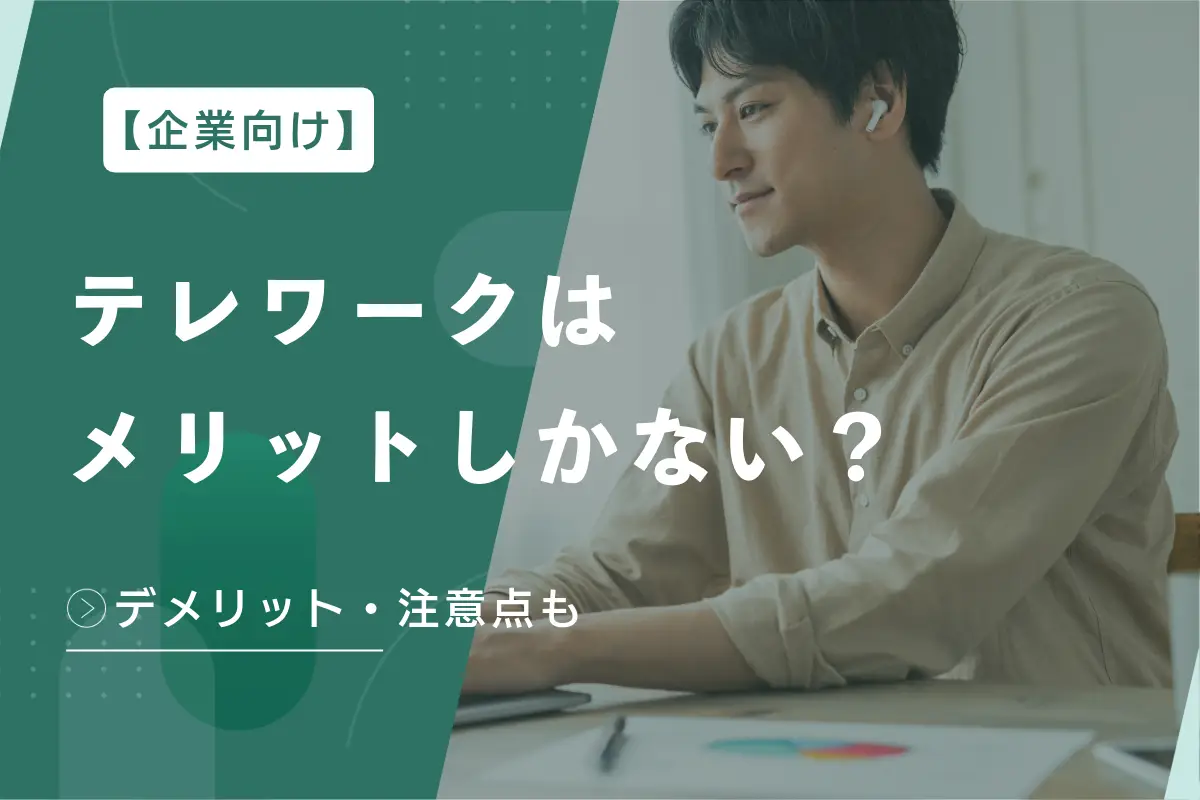「フリーランスか正社員か、自社に合うのはどちらなのか?」そんな悩みを抱えた企業も多いのではないでしょうか。
柔軟な契約とコスト管理が可能な「フリーランス」と、組織への定着や育成がしやすい「正社員」、それぞれ異なる魅力があるからこそ選択に迷うのも無理はありません。フリーランス(業務委託契約)と正社員雇用、どちらの雇用形態で進めていくかは企業の事業フェーズやリソースの上限がキーになります。
本記事では、フリーランスと正社員の違いやメリット、注意点など、幅広く解説します。さらに、フリーランスからの正社員転換「トランジション採用」も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
正社員の副業実態とフリーランス経験者を上層メンバーに迎える利点
労働政策研究・研修機構による最新の調査では、副業をしている人の中で、本業が正社員の人は約38%と判明。これは非正規社員と、ほぼ同じ割合となっており、その差はわずか数パーセントです。
上記の結果から、本業が正社員で副業をしている人は、副業人材全体の割合を見ても多いことがわかります。特にIT・クリエイティブ業界では、クラウドソーシングサービスやSNSを活用し、週末や隙間時間に副業しているケースが多いです。具体的にはライティングや動画編集、プログラミングなど、在宅かつオンラインで完結できる仕事が人気を集めています。
また、副業・フリーランス経験者を、企業の上層メンバーに迎えるメリットはいくつかあります。まず多くの外部人材は、自ら仕事を獲得して責任を持って業務遂行してきた人たちです。そのため自己管理能力や課題解決力が求められる場面で、高いパフォーマンスを発揮するでしょう。
加えて新規事業の立ち上げや業務改善など、社内に新たな視点や刺激をもたらしたい場合でも活躍が期待できます。
フリーランスと正社員の5つの違い
フリーランスと正社員、それぞれ「どちらが自社に適しているのか」を判断するには、これらの違いを理解しておきましょう。以下の表では、フリーランスと正社員の違いについてまとめました。
比較項目 | フリーランス(業務委託契約) | 正社員(雇用契約) |
契約・報酬形態 | 業務委託契約に基づき、成果物や稼働に応じて報酬が支払われる | 雇用契約に基づき、毎月固定の給与が支払われる |
社会保険・税金 |
|
|
適用される法律 | フリーランス新法など | 労働基準法や労働契約法など |
働き方 |
|
|
契約終了時 |
|
|
次の章ではさらに詳しく解説していきます。
1. 契約・報酬形態
フリーランスとは業務委託契約を結び、契約内容に応じて報酬を支払います。報酬は成果物や稼働時間に基づいて支払うため、固定報酬や成果報酬といった案件ごとの柔軟な設計が可能です。契約書では、成果物や納品期日、支払い時期などを明記します。
一方、正社員は雇用契約を結び、一定の給与を支払います。労働時間や業務内容に従い、毎月固定的に支給するのが特徴です。また企業によっては、「成果や業績アップに貢献すればボーナス・賞与が付与される」「残業代あり」といった点も、正社員特有の報酬・支給形式となります。
2. 社会保険・税金
フリーランスの場合、原則、フリーランス本人が国民健康保険や国民年金に加入して手続きします。また毎年、確定申告を通じて所得税や消費税を納税する必要があります。
一方、正社員は企業が社会保険の手続きを行い、給与から自動的に引く形です。企業側が社会保険料を負担するため、社員は手続きが簡便となります。ただし企業は、人事労務や経理に詳しい人材雇用や、専門の部署を用意していく必要があります。
3. 適用対象の法律
フリーランスは業務委託契約やフリーランス新法に基づいて働くため、原則、労働基準法や労働契約法の適用は受けません。最近施行されたフリーランス新法では、一方的な買いたたきや返品などを禁止しています。法令違反しないよう、企業は公正な取引を意識しておきましょう。
一方、正社員採用の場合は、労働基準法や労働契約法に気をつける必要があります。長時間労働の抑制やハラスメント行為の防止など、企業内でのコンプライアンス意識を高めておきましょう。
4. 働き方・業務の進め方
多くのフリーランスが、スケジュール管理やタスク処理のフローを個人で工夫しながら働いています。複数社とやり取りしている点から、企業側はその働き方に配慮した柔軟な対応が求められるでしょう。ひとつ注意点として、「偽装請負」があります。偽装請負とは業務委託契約を締結しているものの、実態として「雇用(労働者)」に近い働き方であると偽装することです。該当すると罰則の対象となるため気をつけましょう。
一方、正社員は企業のルールや方針に従い、決められた勤務時間内で業務を進めます。多くの企業が社員の人材育成や、チームでの目標達成に注力しており、組織の結束力を重要視する傾向があり、依頼する業務の柔軟性が高いのも特徴のひとつです。
5. 契約解除・終了時
フリーランスは契約期間終了と同時に、業務のやり取りも自動的に終了します。契約解除も柔軟で、企業側とフリーランスの合意のもと契約を終了できます。一方的な契約解除は禁止です。半年以上続く契約の場合、解除の事前相談が必須となります。
正社員の場合、解雇や退職に関する手続きが厳格に定められています。企業側が社員を解雇する際は、労働基準法や労働契約法に基づく正当な理由が必要です。解雇予告や退職金、退職手続きなど、企業はその対応を誠実に進めなければいけません。
フリーランス活用と正社員採用のメリット
フリーランスと正社員、それぞれ異なる強みがあります。ここでは、両者を活用する際のメリットを見ていきましょう。
フリーランス活用のメリット | 正社員採用のメリット |
|
|
【フリーランス】即戦力人材をスピーディーに確保できる
多くのフリーランスは専門スキルや豊富な経験を保有しているため、採用後の迅速な実務着手が期待できます。正社員採用と比較して選考期間が短く、業務委託契約を結べば即日〜数日での稼働依頼も可能でしょう。
たとえば「LPを1ヶ月だけ制作してほしい」「広告運用の専門家に数週間だけ入ってほしい」といった、短期的かつ高スキルを要するプロジェクトで有効です。急なリソース不足への対応や、新規事業の立ち上げ時も、外部人材によるサポートで業務を進められるでしょう。
【フリーランス】柔軟な契約とコストコントロールが可能
フリーランスとは業務単位・期間単位で契約できるため、必要な時に必要なだけのリソース確保が可能です。そのため「繁忙期だけの稼働」といった調整もしやすく、予算に応じた契約内容の見直しを図れます。
さらに、社会保険料や福利厚生費が発生しない分、トータルコストを抑えやすい点も魅力です。人件費を変動費化することで、経営に柔軟性が増すでしょう。
【フリーランス】外部視点や専門性を取り入れられる
複数の企業案件に関わってきたフリーランスは、その経験から他社の成功事例や最新トレンドなど、社内にはない知見を持ち込むでしょう。特にマーケティングやUI/UX、エンジニアリングといった分野では、専門性の高い人材が社内で活躍します。
新規プロジェクトの立ち上げや、新しい切り口で課題解決を実行したいときは、社内にはない視点を導入できるフリーランスへの業務委託が有効です。
【正社員】社員は組織への帰属意識が強まりやすい
正社員の場合、企業文化やチームに対する帰属意識が強くなりやすいです。スキルアップ研修や目標設定の提示などから、企業は長期的に社員を育成できるでしょう。
また、社内イベントやミーティングなど、社員のモチベーション維持や働きがいを高めやすいです。そのため、「会社全体の一体感やチームワークの醸成を重要視したい」「長期的に人材を育成したい」と考える企業には正社員採用が適しています。
【正社員】業務指示の自由度が高い
正社員採用では、企業が柔軟に業務指示を出せるのが利点です。プロジェクトの進行に合わせたタスクの変更や、突発的な業務への対応依頼が可能となります。
また、上司や同僚との日々のやり取りから、マネジメント運営や人事評価が行いやすく、業務改善や成果の最大化にも繋げやすいです。そのため「複数タスクの管理や部門横断の仕事を任せたい」といった場合には正社員の方がマッチします。
【正社員】情報管理や組織統制がしやすい
正社員は、就業規則や社内ルールに則って業務を進めるため、情報セキュリティや社内フローの順守といった観点で統制がしやすいです。特に顧客情報や、社内戦略を扱うポジションでは、正社員に任せた方が安心でしょう。
また正社員の場合、評価制度や目標管理制度を元に、行動や成果に対する継続的なフィードバックがしやすいです。「企業内で統一的なオペレーションを構築したい」という場合は、正社員採用をおすすめします。
フリーランス活用と正社員採用における注意点6つ
フリーランス活用と正社員採用では、それぞれ注意点があります。以下の表では、企業側が意識すべき注意点をフリーランス・正社員別に整理しました。
フリーランス活用の注意点 | 正社員採用の注意点 |
|
|
【フリーランス】契約内容を明示する
フリーランスとの契約では、業務委託契約書で「業務内容・納期・報酬・責任範囲」などを明確にする必要があります。双方の認識にズレがあると、のちにトラブルとなるだけでなく、法令違反に該当する恐れがあるため注意しましょう。
たとえば「週2日稼働」と取り決めた場合、「時間単位の対応が必要か」「成果物の納品ベースか」など、書面に記載しておきます。また機密保持契約(NDA)もセットで締結し、口頭やチャットだけのやり取りではなく契約書に沿った業務運用を徹底しましょう。
【フリーランス】コミュニケーション体制を整える
フリーランスと仕事をする場合、コミュニケーションの頻度や手段を事前に決めておくことが重要です。たとえば「週1回のオンラインミーティング」「Slackでの日次報告」など、具体的な連絡ルールを共有しておくと、進捗の見える化や方向性のすり合わせがしやすくなります。
特に、複数の案件を掛け持ちしているフリーランスの場合、連絡が取りづらくなるケースもあります。トラブル防止のためにも、業務開始前に「いつ」「どの手段で」「誰に」連絡するか、といった体制を整えておきましょう。
【フリーランス】外部人材の就業環境を配慮する
フリーランスが社内に常駐する場合や、社内システムにアクセスする場合、働く環境の整備も配慮すべきポイントです。たとえば、作業用PCの貸与や、チャットツール・社内ポータルのアカウント付与などが挙げられます。
また、フリーランスは孤立しやすい立場でもあります。そのため必要に応じて社内メンバーとの顔合わせや定期的な報連相の機会を設けると、成果を最大化しやすいです。外部人材を「チームの一員」として受け入れて体制を整えると、信頼関係も構築できます。
【正社員】採用要件を明確にする
正社員を採用する際は、「どんなスキル・経験・人物像が必要か」といった点を言語化しておきましょう。採用要件が曖昧なままだと、面接基準がブレてしまい、ミスマッチを引き起こします。
たとえば「即戦力エンジニアを採用したい」といった場合、技術スキルに加えて「どのフェーズの開発に携わるのか」「チームリーダー経験は必要か」など、求める要件を具体的に設定しておきましょう。採用要件がクリアになれば、求人票や面接質問も的確になり、質の高い採用活動を進められます。
【正社員】ミスマッチを防ぐ選考フローを取り入れる
正社員採用は長期雇用が前提となるため、ミスマッチを防ぐ選考プロセスが欠かせません。スキル面の確認はもちろんのこと、カルチャーフィットや価値観の共有も重視すべきポイントです。
たとえば複数回の面接に加え、「現場社員とのカジュアル面談」や「業務内容の体験課題」などを取り入れると、入社後のギャップを減らせます。また、面接時には「入社後に求められる働き方」や「評価制度」も伝えると採用の透明性が高まり、双方にとって納得のいく判断がしやすくなるでしょう。
【正社員】入社後の定着を支援する
採用が成功しても、入社後すぐに離職しては意味がありません。定着を支援するには、入社後のオンボーディング実施や、業務マニュアルの整備、定期的な1on1ミーティングなどが効果的です。
また業務面だけでなく、社内コミュニケーションやキャリアパスへの期待など、心理的なケアも重要です。評価制度の透明性や、キャリアアップの仕組みを説明すると、「この会社で長く働けそう」という安心感を与えられます。人材を「採用して終わり」ではなく、「戦力として育てる」ことを意識しましょう。
フリーランスと正社員、迷ったときの選び方のコツ
フリーランスと正社員、それぞれにメリットと注意点があるからこそ、どちらを選ぶべきか迷う場面は少なくありません。どちらが「優れている」というわけではなく、自社の状況や任せたい業務内容によって選択肢は変わってきます。
この章では、迷ったときにチェックしておきたい、フリーランス活用と正社員採用を選択するコツについて紹介します。
任せたい業務の性質から判断する
まず、依頼したい業務の内容から判断するといいでしょう。たとえば、短期的なプロジェクトや専門性の高い業務、成果物ベースで完結する業務であれば、フリーランスが適しています。具体的にはWebサイト制作やシステム開発など、成果物に対して明確な納期とアウトプットがある仕事は業務委託契約が向いています。
一方、継続的な組織との関わりや、マネジメント力・チーム連携が求められるポジションは、正社員の方がマッチするでしょう。曖昧な業務内容では判断が難しいため、任せたい仕事の粒度と期間を具体的に洗い出してから検討するのをおすすめします。
自社の事業フェーズに合わせて選択する
企業の成長段階や事業フェーズによっても、適切な人材の契約形態は変わってきます。創業期や立ち上げフェーズなど、スピード感が求められる場合はフリーランスへの業務委託が最適です。必要なタイミングでスポット的に仕事を依頼できるため、限られたリソース内で柔軟に契約内容を調整できます。
一方、事業が安定・拡大フェーズに入り、チームの一体感や長期的な人材育成を重視したい場合、正社員採用を優先するのが得策です。自社が「今どのステージにあるのか」を見極め、最良の採用手法を選びましょう。
人材採用・育成にかけられるリソースの上限から考える
フリーランスと正社員のどちらにするかは、「どれだけ人件費・工数を投下できるか」といったリソース面も大きな判断材料になります。正社員採用は、求人の出稿や面接、入社後の教育・研修に至るまで、多くの時間とコストがかかります。また、労務管理や社会保険の手続きといったバックオフィス業務の負荷も増えるでしょう。
一方、フリーランスであれば、採用までのリードタイムが短く、即戦力人材を業務単位で確保できるため、リソースが限られている企業に向いています。ただし、発注側が業務内容を明確に整理し、進捗管理や品質確認を実施する必要があるため、そのための社内体制は必要です。採用にかけられる工数・予算から、「どちらの形態が現実的か」を検討していきましょう。
柔軟性の視点から比較する
フリーランスは必要な時期・業務に合わせて契約でき、稼働量も柔軟に調整できるという大きなメリットがあります。たとえば「繁忙期のみ月60時間の稼働を依頼」「リニューアルプロジェクトの3カ月間だけ契約」といった形も可能です。
一方、正社員は契約上の柔軟性は低いものの、役割の変更や人員配置の転換がしやすいといった特徴があります。社内業務への臨機応変な対応や、長期的な育成を求めるなら、正社員がマッチするでしょう。
フリーランスからの正社員転換、トランジション採用をおすすめする3つの理由
近年、初めはフリーランスとして業務委託で働いてもらい、その後に正社員として迎え入れる「トランジション採用」という方法が注目されています。ここでは、トランジション採用の具体的なメリットを3つの観点から紹介します。
採用のミスマッチを防げる
トランジション採用を取り入れると、企業と人材の双方が、実際の業務や社風をリアルに体感しながら採用の可否を判断できます。そのため、入社後に「思っていた仕事と違う」「チームと合わない」といったミスマッチを未然に防げます。
特に正社員採用では、履歴書や面接の印象だけで判断するケースが多く、実際に働き始めてからギャップが生じるケースは少なくありません。トランジション採用なら、実務を通じて人材のスキルレベルやチーム力を見極められ、本人にとっても「この会社で長く働けそうか」と判断できます。こうした相互理解は、入社後のトラブルや早期離職のリスクを減らし、自社に適合する人材とのマッチング率を高めます。
即戦力人材をすぐに採用できる
多くのフリーランスは、特定分野での専門スキルと豊富な実務経験を備えた即戦力人材です。トランジション採用では、そうした外部人材とまず業務委託で協業し、業務理解や企業文化への適応度を見ながら正社員登用できるのが大きな魅力です。
通常の正社員採用では研修やOJTを経て即戦力化を図りますが、フリーランスであれば導入研修を最小限に抑えつつ初日から成果を出すことも可能です。成果を見てから正社員登用を判断できるため、リスクの少ない形で人材を確保できます。
納得度・定着率の高い採用が見込める
一般的な中途採用では面接や数回のやり取りだけで入社を判断しますが、トランジション採用では「実務に入ってから決める」というプロセスを経由します。そのため候補者が、強い納得感を持って入社できます。
また、これまでの仕事で信頼関係の基盤が構築されている点から、円滑なコミュニケーションが可能です。特に業務委託契約が長期だった場合は、候補者が企業のビジョンや方針に強く共感している証とも言えます。そのため、長期的な定着や活躍が期待できます。
フリーランスと正社員に関するよくある質問
ここでは、フリーランスと正社員に関するよくある質問についてまとめました。
本業と副業を両立している人って本当にいますか?
本業と副業を両立している人は実際にいます。たとえば平日は、企業の正社員として勤務し、夜間や週末に副業する人も少なくありません。こうした人材は、スキルアップや収入の増加を目的としており、短期プロジェクトや限られた時間での稼働を希望する場合が多いです。
副業人材に業務を委託する際は、稼働時間や業務内容を明確にし、情報管理や秘密保持などに留意していきましょう。
業務委託契約書には何を明記すべき?
業務委託契約書には、以下のような項目を明記する必要があります。
- 業務内容・範囲
- 報酬金額・支払い条件
- 納期・成果物の仕様
- 守秘義務
- 契約期間と解除条件
これらの取り決めが不十分だと、納品物の品質や納期をめぐるトラブルの原因になるため、契約前に丁寧にすり合わせておきましょう。
フリーランスと正社員、採用コストの面でどちらがお得?
一概に言えませんが、短期的なプロジェクトやスポット業務においては、フリーランスの方がコストを抑えられる傾向にあります。理由は、社会保険料や福利厚生費が不要であることや、業務が終われば契約終了できる柔軟性があるためです。
一方、長期的な雇用や、社内での成長・戦力化を見込みたい場合は、正社員の方がコストパフォーマンスが高くなることもあります。正社員は安定した労働力として育成しやすく、組織への定着やノウハウの蓄積にも貢献してくれるためです。採用目的と事業フェーズを踏まえて、どちらが適しているかを見極めていきましょう。
フリーランス活用・正社員採用のことなら、転職エージェントの『Workship CAREER』におまかせ!
フリーランスと正社員、それぞれの違いやメリットを理解した上で、人材をどう確保するかは、企業の成長を左右する大きなポイントです。業務の特性や自社のフェーズ、採用にかけられるリソースを見極めつつ選択していきましょう。
転職エージェントの『Workship CAREER(ワークシップキャリア)』では、フリーランス人材を正社員として迎える「トランジション採用」を支援しております。約5万人以上のフリーランスネットワークから、自社にマッチしたIT・DX人材をご紹介いたします。
Workship CAREERの特長
- トランジション採用の導入:業務委託契約からスタートし、その後正社員登用への切り替えをサポートいたします。
- 豊富な人材データベース:エンジニア、デザイナー、PMなど、約5万人以上のフリーランスネットワークから、企業のニーズに合った候補者をご紹介いたします。
- 人事のプロが採用から育成まで一貫して伴走:定例会議やスポット対応など、貴社の人事課題をトータルに解決いたします。
Workship CAREERでは貴社の採用課題や募集内容をヒアリングした上で、最適な人材をご紹介いたします。無料相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。
- Workship CAREERのサービス内容
- ご契約の流れ
- 取引実績
- 関連サービス

リモートワーク・ハイブリッド勤務に特化した人材紹介エージェント「Workship CAREER」の編集部です。採用に役立つ情報を発信していきます。